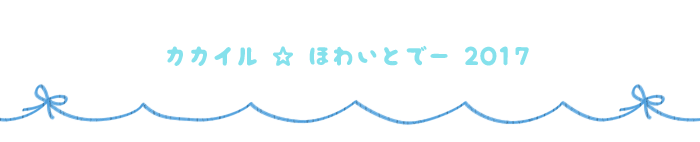なないろ「マカロン ~特別な人~」
「こんにちは」
「ああ、イルカ先生!いらっしゃい!」
振り返った八百屋のおばちゃんにイルカは笑顔を見せた。
「おお先生。今帰りかい」
野菜が入った段ボールを運んでいた店主も、イルカに気が付き笑顔を見せる。
「はい。今日はもう」
一ヶ月前にぎっくり腰で痛めた腰も、すっかり良くなった店主に、イルカは笑顔で応えた。
今日の献立を頭に浮かべながら野菜を眺める。
「先生、お待たせ」
先客の対応を終えたおばちゃんに、イルカは野菜を指さした。
「にんじん2本と、じゃがいもも2つ。ブロッコリーも1つください」
「ああ、カレーだね」
玉葱は?と聞かれイルカは首を横に振った。
「まだ家にあるんで、大丈夫です」
「まあ男の一人暮らしに余分にあっても腐らせるだけだからねえ」
あんたらの家業は大変なんだろうけどさ。
言われてイルカは苦笑した。
忍びと言う職業柄任務になれば家におらず仕方なくと言うのもあるのだが。自分は実状内勤の教師だ。それでも一人暮らしとなれば使う量も少ないし、つき合いで飲みに行く事だってある。自ずと自炊が減り、結果腐らせる事もあった。
「はい、350円ね」
イルカは笑顔で頷くと財布を開く。小銭が丁度あったからそれを彼女に手渡した。
「はい、丁度」
前掛けのポケットに小銭をしまいながら、ああ、そうそう、と、彼女は思い出したように顔を上げた。
「この前一緒に買い物に来た子、今日はいないんだね」
子、と言われて考えて、それがすぐにカカシだと思い当たったイルカは笑った。まあ彼女からしたら、自分もカカシも子供ぐらいの年齢だっておかしくはない。
カカシは今日用事がある。それは今日受付で、七班の任務報告で顔を合わせた時にそう聞いていた。
今日用事があって一緒に帰れないんです。
申し訳なさそうに言われてイルカは笑顔で首を振った。カカシにも用事があるくらい当たり前だ。
「ええ、今日は」
そう答えると、へえ、と彼女が相づちを打った。
「あ、デートだね。あれはいい男だもんね。顔ほとんど見えてないけど分かるよ」
彼女のするどい審美眼に、イルカはまた苦笑いを浮かべた。
「イルカ先生もさ、早く相手を見つけなさいよ」
「....まあ、...その....」
不意に話が自分に変わり、イルカは笑って誤魔化そうと頭を掻く。
「おいおい、余計な事言って先生を困らせるんじゃねえよ」
後ろで聞いていたのか、店主のその助け船にイルカはほっとして、じゃあ、と頭を下げてそそくさと店から出た。
危ない。
あのままいたらきっと見合い話でも持ってきそうな勢いだった。
イルカは息を吐き出しながら商店街を歩いた。
どうもあの年齢の人が相手だと、自分のいつもの調子が出ない。母親に近いから、と言うのもあるんだろうが。
袋を下げながら、リンゴも買い忘れたと思い出したが仕方がない。それに今更あの店に今日は顔を出す勇気はない。
まあ、なくても朝食はパンで済ませればいいだけだ。
自分の中ではパンと珈琲があれば十分な朝食だ。
それにしても。イルカはふとさっきの会話を思い出した。
彼女の審美眼は正しいが、彼の恋人がまさか自分だとは思ってもいなかった。
それにイルカは微かに眉を寄せた。
薄々気が付いてはいたが。カカシは同性とか異性じゃないからとか、そう言うところに偏見も何もない。だからおおっぴらに二人の関係を隠す事だってしない。
だからカカシは自分の気持ちを素直に伝えてきた。
そこだ。
イルカは嘆息した。
カカシの想いと自分の気持ちにようやく向き合えたのに。
結局自分は人の目を気にしている。
(...駄目だよな)
いっそホモだって周りに言っちゃえば気が楽になるのか。
友人や職場の同僚や上司、生徒、生徒の親。
自分の周囲の人間がもやもやと頭の中で浮かぶ。
(....勇気ねえ....っ)
そこからの想像をして、イルカは苦しそうな顔で落ち込むしかなかった。
視線を地面から上げた時、視界に入った銀色に目を留めた。顔を上げる。
イルカはじっと先にいる人間を見た。
間違いようがない。
カカシだ。
用事があるって、ここでだったのか。
痩身長身のカカシは自分より少し背が高い。手をポケットに入れるのは彼の癖のようなものだ。
ーーしかし。
イルカは首を傾げた。
隣にいる女性は一体誰だろうか。二人で洋菓子の店の前で何かを話している。そこは最近出来たばかりの洋菓子店だった。
少し前、サクラがそこの店のお菓子が宝石みたいで綺麗で美味しいと、鼻息荒く説明してきた事を思い出した。
女の子らしい内容だと微笑ましく話に耳を傾けたのだが。
その店の前にいるカカシと、ーー見たことのない女性。服装からして忍びには間違いないが。受付をしている自分でも見たことがない顔だ。
じっとその横顔を見つめながら、どこかで見たことがある気もするが。イルカは考えるように顎に手を当てる。
カカシに視線を動かし。
眉根が寄っていた。
(何だあの顔)
眉を下げて情けない笑顔を見せるカカシに困惑する。
と、女がカカシに手を伸ばして腕を取った。引っ張りカカシと一緒に洋菓子店に入って行く。
イルカはただ、その様子をじっと眺めるしかなかった。
「イルカ先生」
イルカの気配に気が付いたカカシが椅子から立ち上がった。
お昼を一緒に食べようといつものラーメン店で待ち合わせていた。
昨日の今日でどんな顔をしていいのか分からないイルカを前に、カカシは嬉しそうな笑顔を見せる。
その顔を見てイルカは余計に複雑な気持ちになった。
「先生。座って」
「あ、はい」
促されるままに座ると、カカシも隣に腰を下ろす。
いつも通りのにこやかな笑みをイルカはチラと横目で窺った。本当にいつも通り過ぎて、嬉しそうな微笑みを浮かべるカカシ。
でも。
それって、昨日もそんな感じだったんじゃねえか?
「...イルカ先生?」
「あ、はいっ」
カカシの顔を見つめながら思考の波にいたイルカは、引き戻される。
慌てて返事をするとカカシが不思議そうな顔をしていた。
「先生は?」
「...え?」
聞き返すと、カカシは目の前にあるメニューを指さした。
「俺は醤油にするけど、イルカ先生は?」
メニューを聞かれていたのか。全然耳に入っていなかった。メニュー表へ急いで目を向ける。
「えっと...俺は味噌にします」
「じゃあその二つ。お願い」
カカシの注文に店主が元気よく返事をした。
「先生、どうかしたの?」
聞かれてイルカはギクリとした。カカシへ顔を向けると、少し心配そうな目でイルカを見ている。
「いや、別に...どうもしてないですよ」
笑ってカウンターに置かれたグラスを手に取ると水を飲んだ。
それでもカカシはイルカの顔を見つめる。
「何かあった?」
「えっと....」
何かあったって。
(そりゃあ...それは。カカシさんが昨日見たこともない女性と一緒にいて、腕とか組んでたからとか、...って言えるわけないだろうがっ)
口に出来ない言葉を飲み込むとイルカはコップの水をがぶがぶと全部飲み干す。
「イルカ先生?」
「いえ、何でもないですっ」
強く言い切られカカシはまた不思議そうにイルカを窺っている。イルカは気まずそうに唇を噛んだ。
何もやましい事がないからカカシは堂々をしているのだ。だから何も気にする必要なんてない。
それでもちらちら昨日の情景が頭にちらつく。
「おまちっ」
眉を寄せたままのイルカの目の前にラーメンが置かれる。
「いただきますっ」
イルカは手を合わせ言うと、割り箸を取り割って勢いよく食べ始めた。
食べ終わりカカシが会計を済ませようとしてイルカは慌てた。
「いいです。俺が払いますっ」
「いいよ、大丈夫」
カカシは優しく微笑んだ。
いつもだったらいいかな、と思うけど、今日は嫌だった。どうしても払いたい。こんな気持ちのままカカシに奢ってもらっても嬉しくない。
「だったら自分の分だけでも俺払いますからっ」
そう言った時、カカシは、え?、とイルカを見た。
「でも、この前イルカ先生が出したんだよ?だから今度は俺だって、二人で話したじゃない」
そこで思い出す。そう言えばそんな事話したのはつい数日前だった。
「そうでしたね...すみません」
ぺこりと頭を下げた。
「お待たせ」
会計を済ませてるあいだ外で待っていたイルカの横に、カカシがくる。
「ごちそうさまです」
「いいえ」
にこと微笑まれて、イルカも合わせるように微笑んだ。
二人で歩きだしながら、無言のイルカをカカシはしばらく見つめて。そこからひょいと隣からイルカの顔を覗いた。
「イルカ先生。いい加減教えてよ」
どうしたの?
優しい声。
カカシは素直に心配している。
目線を上げれば、その通りで、カカシの心配そうな眼差しをイルカに向けていた。
「変だよ?」
「変ですかね...」
そりゃそうだろうなあ、と力なく微笑みながら答えた。
「だって店でもあんなに水のんじゃって。普段あんなに飲まないじゃない」
気持ちが落ち着かなくて、誤魔化すのもあって飲んでいたのは確か。
でもこれが酒だったらいいのに、と思っていた事にイルカはまた眉を寄せた。
そんな事を思うのは、自分が逃げたいからだ。
そこに気が付きイルカは情けない気持ちになる。
「もー俺恋人なんだよ?言ってくれないなんて寂しいなあ」
カカシは口布の下で口を尖らせたのが分かった。
そうだよな。俺はカカシさんの恋人なんだ。
カカシの口から出た言葉だけで胸が暖かくなり同時に締め付けられる。
「カカシさんっ」
急に立ち止まって名前を呼ばれ、カカシは驚いてイルカを見た。
「うん、...どうしたの?」
勇気を振り絞るように、イルカは握った拳に力を入れた。
「俺、昨日見たんです....その、夕方...商店街で...女性の方と一緒で、」
「え!?」
言い掛けてる時にカカシが驚いた声を上げた。
「昨日って...イルカ先生いたの?」
「ええ...俺買い物で八百屋に」
カカシが驚いた顔をするのは何故だろう。
そこは上忍仲間と約束があって、とか。そんな言葉を想像していたのに。
カカシはそこから眉を寄せた。明らかに困った顔をしている。
あれ、想像してたのと違う。
「...俺に見られたらまずかったって事ですか...」
静かに問うイルカに、カカシはぶんぶんと手と首を振った。
「いや、そうじゃないんだけど。だって、先生に見られるなんて思ってなくて」
「...思ってないなら何ですか」
厳しい目になるイルカに、カカシは困った顔をする。
「違うっ、違うよ?俺はただ仲間に相談してただけで」
「相談?相談だったらまず最初に俺に言ってくれればいいでしょう」
さっきカカシさん恋人だからって、そう言いましたよね。
だんだんと険しい顔になるイルカに、カカシは、参ったな、と呟いて頭を掻いた。
「えっとね。だって...ほらイルカ先生ちゃんと答えてくれなかったから」
ん?と、イルカは首を傾げた。
「答えるって、何をです?」
「ほら、この前。俺聞いたじゃない。バレンタインのお返し何がいいかって」
言われて思い出す。
イルカ先生何か欲しいものってある?
先週の帰り道、カカシにそう聞かれた。
「いえ、何も」
基本物欲がない自分に、すぐに欲しいものはなかった。だから首を振る。
「何でそんな事聞くんですか?」
聞き返すと、カカシは頬を少しだけ赤らめて頭を掻いた。
「え~、だってほら。もうすぐホワイトデーだから」
一瞬イルカはきょとんとして。それから笑い出した。
「え、なに?そこ笑う?」
何で、大事でしょ、と言うカカシを見て笑って。
「俺バレンタインに野菜しか渡してないんですよ?何も貰えませんって」
チョコを改めて渡すのも恥ずかしく、あれから何も渡していないのに。
カカシの律儀なところが妙に可愛く見える。
「あれはイルカ先生の優しさでいただいた報酬なんです。チョコより価値があります」
真面目な顔をされ、イルカはいい加減吹き出した。
「そうですね。でも、欲しいものは何もないですから」
「え、本当に?」
「はい」
きっぱりと言うと、カカシは困った顔をした。
「そっか」
「気持ちだけで十分です」
確か、そんな話だったはずだ。
その会話はちゃんと覚えている。でも。そこから昨日のカカシと何が関係あるのか。
「...確かに、聞かれましたね。でも俺何もいらないって答えましたけど」
胡乱な眼差しで見つめると、カカシはため息を吐き出した。
「そうですが。やっぱ何かあげたいなあって、思って」
「だから仲間に聞いたって事ですか」
少し申し訳なさそうにしているカカシに言えば、小さく頷いた。
「ほら、お菓子詳しい子だったから、色々教えてくれるって言うし」
だから選んでもらったんですよ。
へら、と笑って言う。
「...選んでもらったって...買ったんですか?」
不意の問いに、カカシは一瞬きょとんとして、すぐにまた嬉しそうに頷いた。
「はい、買うって言うか、予約ですが」
カカシの説明(言い訳)に、イルカは明らかに苛立った。
カカシの言っている事は分かる。何もいらないと言われて。でも何かをあげたいと、思ってくれたから。
それでも。それは違う。カカシの自分を思う気持ちに傷ついていると言うのに。
それを分かっていないカカシにも腹が立った。
怒っちゃいけない。カカシは悪気がない。
それは分かっている。
でも。
「どうして...」
イルカは我慢できずに口を開いていた。
「どうして...他の人に選ばせるんですか」
「え?」
「そうでしょう?確かに俺が何か欲しいって伝えなかったのも悪いと思います。だからって、思いつかないからって、他の人に選ばせるなんて。それで俺が喜ぶとでも思ったんですか?」
驚いて目を丸くするカカシはまた、え?と聞き返す。イルカは唇を噛んだ。
「カカシさん俺に言いましたよね?大根でも人参でもブロッコリーでも何でもいいいって。俺からもらえるものなら何でも嬉しいって。それは俺も同じなんですっ。そんな事も分からないんですか?」
荒だった声で言い終わるイルカはカカシを睨む。
カカシは。すごい剣幕のイルカを見つめながら、親に叱られている子供のような顔をした。
「....でも....」
「そうじゃないですか。あんな風に腕を組んで、」
「いや、だって、あれはですね、」
カカシの言葉にイルカは睨んだ。
「でもとかだってとか。言い訳なんて聞きたくないです」
そう言い捨てるとイルカはカカシを置いてアカデミーへ歩き出す。
「イルカ先生、」
「ついてこないでください」
イルカの声に、そこからカカシは何も言わなかった。ついてもこなかった。
その週末はホワイトデーだった。
あれからイルカはカカシを無視している。受付や放課後に顔を見せるが、挨拶だけすると、イルカはそのままカカシが何か言う前に顔を背けていた。
ちょっと、怒りすぎたと思う。
分かっている。
悪気がない。
だからあんなに怒ることはなかったんだ。
ただ、あの時の女といる時の嬉しそうな顔とか。腕を組んでるところとか。忘れなきゃいけない情景ばかり頭に浮かび。それを思い出すとどうしても自分からカカシに声をかけずらかった。
昨日はカカシは姿を見せなかったのは、任務だと、執務室で知った。
それで気が付けば今日はホワイトデー。
イルカは顔を顰めた。ため息を吐き出して立ち上がる。
「イルカ先生もうお帰りですか?」
鞄を肩にかけたとろこで声をかけられる。
「ええ、まあ」
イルカは眉を下げて力なく微笑んだ。
お疲れさまです、と背を向けた女性教員がイルカに振り返った。
「ああ、そうそう。今日はお菓子ありがとうございました」
嬉しそうな彼女の顔を見て、イルカは頭を掻いた。
「いやそんな。あんなものでよかったですかね」
「もちろん。私クッキー好きなんです。また休憩の時にいただきますね」
会釈して去っていくのを見送って。イルカは息を吐き出した。
律儀と言われればそれまでだが。貰ったのに返さない訳にはいかない。
それは、きっとカカシもそうだったに違いない。
分かっている。頭では。
「さてと」
イルカは鞄をしょいなおすと職員室を後にした。
そのままイルカは外に出てそのまま上忍待機所に向かう為に足を向ける。
今日はたぶんそこにいると、調べたから。
だから。こうして早めに上がってカカシに会いに行って。
謝ろう。
でも足取りは重い。
少し俯き廊下を歩きながら、イルカは生徒の声がする窓の外へ顔を向けた。
子供達が嬉しそうに笑いながら歩いている。その楽しそうな姿を眺めた。
(素直じゃねえんだよな、俺は)
無邪気に笑い合う子供達を見ていたら、比べようもないのに自分と子供を重ねて、情けない気持ちになった。
喧嘩したらまず自分から謝れって、生徒に言ってるのに。
(いや、あれは先生が悪いんじゃなくて、俺は謝ろうと思ってるわけで)
誰にでもなく心の中で生徒に言い訳して、イルカは頭を振った。
ぐじぐじしてるなんて俺らしくない。
カカシと出会ってから、見たこともない情けない自分がいる事に気が付かされている。
こんな女々しいなんて。
カカシを好きと思うだけで、胸が痛いくらいに苦しい。
ゆっくり歩いていても上忍待機室まではすぐだった。
扉の外から中を覗くと、見えるのは銀色の髪。
それだけで心臓がが早く打ち出す。とくとく、と高鳴る心臓を抑えるようにベストの上から抑えて。
イルカは扉を開けようとして。カカシが顔を上げた。それはイルカに気が付いたからじゃない。
奥にいた誰かが声をかけたからだ。
そこには見覚えのある若いくノ一。
(また....)
最悪のタイミングにイルカの気持ちがみるみる沈む。
そのくノ一は何か言いながらカカシの腕を急かすように引っ張った。それでもカカシは椅子に座ったまま動かない。断るように手を振る。
何を話しているのか。読唇術をすればいいことなのだが、目の前の二人で頭がいっぱいいっぱいでそこまで頭が回らない。
腕を引っ張られていたカカシが立ち上がった。何か話し始める。
しばらく話して、くノ一が扉に振り返った。
隠れなくてもいいはずなのに。イルカは慌てて身を隠していた。
柱の陰に隠れてすぐ、くノ一は勢いよく部屋から出ていく。見つかったら覗き見をしていたんだと勘違いされてもおかしくはない。自分の存在に気が付かれなかった事に安堵してイルカは息を吐き出した。
そこでイルカは考える。
ーー今度はなんだろう。
少し二人で言い争っていたような感じだった。
何にせよ、見たくないものを見たなあ。
酷く憂鬱な気持ちになる。
でも。
それとこれは別だ。
俺は謝ると決めたんだ。
イルカは意を決するように息を吐き出し。立ち上がる。再び上忍待機室の扉に向かった。
「失礼します」
ノックして扉を開ける。
カカシが驚いて椅子から立ち上がった。
「イルカ先生!」
「こんにちは。今いいですか?」
問いかけると、カカシは先日怒られた時のような顔でイルカを見た。頭をがしがしと掻く。
「あのね、先生。この前の事なんだけど、」
「いえ、カカシさん。先に言わせてください」
言葉を遮るようにして手のひらを見せる。カカシは口を閉じた。
「この前は俺が言い過ぎました。すみません」
深く頭を下げると、カカシが慌てた。
「ちょっと、やめてよ。悪いのは俺です」
「でも言い過ぎた事には変わりありませんから」
だからって、頭上げてよ。ね、イルカ先生。
カカシの手がイルカの肩に乗せられ、そこでイルカはゆっくり頭を戻す。
困った顔でじっとイルカを見つめていた。
「俺も、ごめんね。イルカ先生に言われて。その通りだって思った」
「......」
「イルカ先生が喜ぶかなって、そればっか先に考えて。そしたらそれ以前の問題でしたね」
情けない笑顔を見せて眉を下げる。
イルカは小さく微笑んで首を振った。
「いえ。もうその事はいいんです。...さっきの喧嘩されてた女性も、傷つけてしまったんじゃないですか?」
聞くと、カカシは目を見開いた。
「え?さっきの?先生見てたの?」
イルカは力なく微笑む。
「ええ、丁度見たって言うか、見えてしまって、」
カカシは困ったように眉根を寄せた。
「そうですか」
「で、何を話されていたんですか?」
カカシは、う~ん、と唸ってからイルカに微笑んだ。
「いや、予約してたお菓子。それはもう取りやめて自分で考えようって決めたんです」
「はあ」
「でもそれをさっき言ったら怒っちゃって」
「怒る?」
聞くとカカシは頷いた。
「うん。あれじゃなきゃ絶対駄目だって。もうすごくしつこかったからそんなに欲しいならあげるから取りに行けば、って言ったら、怒って出てっちゃったんです」
「え?」
「え、だから、」
「ちょっとちょっと待ってください」
カカシはイルカの言葉に、ん?と首を傾げた。
「お菓子をその女性に取りに行かせたんですか」
「...はあ」
「はあ、ってそれはカカシさん。あなたが彼女にお願いして選んでもらって、予約したんでしょう?だったら自分で取りに行かないでどうするんですか」
イルカの徐々に帯びる怒りに、カカシは肩を竦めた。
「まあ...そうですけど、...でもね、」
「でもとかだってとか、俺はそんな言葉聞きたくないんですっ」
「ちょーーとまったーーー!!」
バン、と大きな音を立てて扉が開く。
振り返るとさっきのくノ一が肩で息をして立っていた。
「また喧嘩してたんですか?」
驚くイルカに構わず女はそう言うと待機所に入ってくる。
「喧嘩はよくないって言ったじゃないですか」
呆れたような口調でカカシを見ると、カカシは眉を下げて笑った。
「はい、カカシ先生。ちゃんと買ってきました」
手に持っていた包みをカカシに差し出した。
クリーム色の綺麗な包装紙。天使の柄があの新しい洋菓子のイメージとぴったりだった。
ラメの入った綺麗なリボンで包まれている。
これがこの女性が選んだお菓子か。
(.....ん?)
イルカは眉を寄せた。目の前にいる女性を見る。
「今....カカシ先生って、言いました?」
聞くと、そのくノ一は、はい、と素直に頷く。
くノ一がカカシさんを先生?聞いた事がない。
眉を顰めたままのイルカに、
「あ、そっか」
そう呟いて胸の前で印を組んだ。
煙が上がる。
そこには。桜色の髪が見えた。
「さ、サクラっ!」
どこかで見たことがあるとは思ってはいた。でもそれは、サクラが変化の授業中に見せた姿だった。
それを今、ようやく思い出す。そして驚く。
「サクラじゃないか!」
もう一度名前を呼ばれて驚いたままのイルカに頭を下げた。
「先生、こんにちは」
「こ、こんにちはって。お前、...じゃあ、あのこの前カカシさんと一緒にいたのって」
「はい。私です」
サクラがにっこり微笑んで答える。
はあ~、と嘆息してカカシが手を顔に当てた。
「ごめんね。先生。俺が相談したのってサクラだったんですよ」
「ええ!?」
驚きの眼差しはカカシに移る中、カカシは続ける。
「そしたらあそこの店のあのお菓子じゃなきゃ絶対に駄目、とか言われてさ。俺は甘いの苦手でよく分からないし。でもサクラはこの前この店の話をしたら、イルカ先生すごく食べたそうにしてたって言うじゃないですか。だから俺はサクラが言うならそれでいいかなって」
そこまで言うとサクラが腰に手を当てた。
「それなのに、カカシ先生。あんな店恥ずかしいから一人で買いに行けない、なんて言うんですよ?一緒に行くって言っても部下とは行きたくないとか言うし。信じられないったらないんだから」
だから私が一肌脱いだんです。全くしっかりして欲しいわ。
そう言うサクラは、丸でしっかりしたお母さんのような口調になっている。
カカシはまた笑って頭を掻いた。
それなのに、と、そこからサクラは呆けた顔になっているイルカに顔を向けた。
「イルカ先生と喧嘩しちゃったからもうそこのお菓子はいらないって、それって酷くないですか?」
もう。喧嘩なんて、やめてください。
強い口調に、イルカは、はい、と返事をする。
「ここのお菓子雑誌にも載ってお墨付きの美味しさなんです。絶対食べてくださいね」
「わ、分かった」
イルカが頷くと、サクラは満足したように息を吐き出した。
「じゃあ私はもう帰ります。もしかしたらサスケくんお返しくれるかもしれないしっ」
そこで初めて子供の表情に戻り、頬を赤らめる。頭を下げサクラは部屋から出ていった。
どうかね~、とカカシが呟いたのはサクラの気配がなくなった後だった。
上忍待機室に残された二人。
イルカはゆっくりと椅子に座って頭を抱えた。
今さっき過ぎ去った事を再生し。それだけで顔が赤くなる。同時に消えてしまいたい気持ちになる。
カカシは部下の気持ちを汲んでいただけで。しかも俺はその相手に嫉妬して。しかもそれがサクラで。
しかも。サクラがカカシと自分の関係を知って。
「...イルカ先生?」
イルカの隣に座ったカカシに、がばっと顔を上げる。
「何でサクラに言ったんですか!?」
泣きそうな顔のイルカにカカシは眉を下げて微笑んだ。
「言ってないですよ。ただ、イルカ先生は何が好きかって、ちょっと聞いただけなんです」
だって、サクラはイルカ先生の教え子でしょ?
「...はい...」
ふくれたままの顔で小さく答えるとカカシはにこっと笑みを浮かべた。
「ナルトだけじゃない。サクラだっていつも俺にあなたの事を話してくれるんですよ。だから、きっといいアドバイスくれるって、俺はそう思ったんです。まあ、結果的にごり押しで決められちゃいましたけど」
そこでまたカカシが笑った。
だから決して他人に選ばせるつもりはなかったんです。
イルカはむくれたままその話を聞いて。
アカデミーから巣立った生徒と、その新しい担当になった上忍師のカカシの気持ちを知って。嬉しくないわけがない。
「....分かりました」
頬を赤らめて呟いた。
結局サクラにばれたからって、カカシを嫌いになる訳がないんだから。
この人が好きだ。
それは隠さない。
カカシが口布を下げ顔が近づく。
それがどんな意味か。
イルカは薄く口を開いてカカシの唇を受け止めた。
触れては離れ、何度もそれを繰り返す。
それだけで心が満たされていく。
(...初めてのキスが上忍待機室か...)
甘いムードに流されながら、イルカはカカシの首に腕を回した。深く口づける。
その横に置かれた可愛いお菓子の箱。
中身はマカロン。ーー特別な人。
その意味を知っているのはサクラだけ。
スキップして帰りながら、秘かにガッツポーズしたサクラを、二人は知らない。
<終>
拍手ボタンを4/3に撤去いたしました。
「ああ、イルカ先生!いらっしゃい!」
振り返った八百屋のおばちゃんにイルカは笑顔を見せた。
「おお先生。今帰りかい」
野菜が入った段ボールを運んでいた店主も、イルカに気が付き笑顔を見せる。
「はい。今日はもう」
一ヶ月前にぎっくり腰で痛めた腰も、すっかり良くなった店主に、イルカは笑顔で応えた。
今日の献立を頭に浮かべながら野菜を眺める。
「先生、お待たせ」
先客の対応を終えたおばちゃんに、イルカは野菜を指さした。
「にんじん2本と、じゃがいもも2つ。ブロッコリーも1つください」
「ああ、カレーだね」
玉葱は?と聞かれイルカは首を横に振った。
「まだ家にあるんで、大丈夫です」
「まあ男の一人暮らしに余分にあっても腐らせるだけだからねえ」
あんたらの家業は大変なんだろうけどさ。
言われてイルカは苦笑した。
忍びと言う職業柄任務になれば家におらず仕方なくと言うのもあるのだが。自分は実状内勤の教師だ。それでも一人暮らしとなれば使う量も少ないし、つき合いで飲みに行く事だってある。自ずと自炊が減り、結果腐らせる事もあった。
「はい、350円ね」
イルカは笑顔で頷くと財布を開く。小銭が丁度あったからそれを彼女に手渡した。
「はい、丁度」
前掛けのポケットに小銭をしまいながら、ああ、そうそう、と、彼女は思い出したように顔を上げた。
「この前一緒に買い物に来た子、今日はいないんだね」
子、と言われて考えて、それがすぐにカカシだと思い当たったイルカは笑った。まあ彼女からしたら、自分もカカシも子供ぐらいの年齢だっておかしくはない。
カカシは今日用事がある。それは今日受付で、七班の任務報告で顔を合わせた時にそう聞いていた。
今日用事があって一緒に帰れないんです。
申し訳なさそうに言われてイルカは笑顔で首を振った。カカシにも用事があるくらい当たり前だ。
「ええ、今日は」
そう答えると、へえ、と彼女が相づちを打った。
「あ、デートだね。あれはいい男だもんね。顔ほとんど見えてないけど分かるよ」
彼女のするどい審美眼に、イルカはまた苦笑いを浮かべた。
「イルカ先生もさ、早く相手を見つけなさいよ」
「....まあ、...その....」
不意に話が自分に変わり、イルカは笑って誤魔化そうと頭を掻く。
「おいおい、余計な事言って先生を困らせるんじゃねえよ」
後ろで聞いていたのか、店主のその助け船にイルカはほっとして、じゃあ、と頭を下げてそそくさと店から出た。
危ない。
あのままいたらきっと見合い話でも持ってきそうな勢いだった。
イルカは息を吐き出しながら商店街を歩いた。
どうもあの年齢の人が相手だと、自分のいつもの調子が出ない。母親に近いから、と言うのもあるんだろうが。
袋を下げながら、リンゴも買い忘れたと思い出したが仕方がない。それに今更あの店に今日は顔を出す勇気はない。
まあ、なくても朝食はパンで済ませればいいだけだ。
自分の中ではパンと珈琲があれば十分な朝食だ。
それにしても。イルカはふとさっきの会話を思い出した。
彼女の審美眼は正しいが、彼の恋人がまさか自分だとは思ってもいなかった。
それにイルカは微かに眉を寄せた。
薄々気が付いてはいたが。カカシは同性とか異性じゃないからとか、そう言うところに偏見も何もない。だからおおっぴらに二人の関係を隠す事だってしない。
だからカカシは自分の気持ちを素直に伝えてきた。
そこだ。
イルカは嘆息した。
カカシの想いと自分の気持ちにようやく向き合えたのに。
結局自分は人の目を気にしている。
(...駄目だよな)
いっそホモだって周りに言っちゃえば気が楽になるのか。
友人や職場の同僚や上司、生徒、生徒の親。
自分の周囲の人間がもやもやと頭の中で浮かぶ。
(....勇気ねえ....っ)
そこからの想像をして、イルカは苦しそうな顔で落ち込むしかなかった。
視線を地面から上げた時、視界に入った銀色に目を留めた。顔を上げる。
イルカはじっと先にいる人間を見た。
間違いようがない。
カカシだ。
用事があるって、ここでだったのか。
痩身長身のカカシは自分より少し背が高い。手をポケットに入れるのは彼の癖のようなものだ。
ーーしかし。
イルカは首を傾げた。
隣にいる女性は一体誰だろうか。二人で洋菓子の店の前で何かを話している。そこは最近出来たばかりの洋菓子店だった。
少し前、サクラがそこの店のお菓子が宝石みたいで綺麗で美味しいと、鼻息荒く説明してきた事を思い出した。
女の子らしい内容だと微笑ましく話に耳を傾けたのだが。
その店の前にいるカカシと、ーー見たことのない女性。服装からして忍びには間違いないが。受付をしている自分でも見たことがない顔だ。
じっとその横顔を見つめながら、どこかで見たことがある気もするが。イルカは考えるように顎に手を当てる。
カカシに視線を動かし。
眉根が寄っていた。
(何だあの顔)
眉を下げて情けない笑顔を見せるカカシに困惑する。
と、女がカカシに手を伸ばして腕を取った。引っ張りカカシと一緒に洋菓子店に入って行く。
イルカはただ、その様子をじっと眺めるしかなかった。
「イルカ先生」
イルカの気配に気が付いたカカシが椅子から立ち上がった。
お昼を一緒に食べようといつものラーメン店で待ち合わせていた。
昨日の今日でどんな顔をしていいのか分からないイルカを前に、カカシは嬉しそうな笑顔を見せる。
その顔を見てイルカは余計に複雑な気持ちになった。
「先生。座って」
「あ、はい」
促されるままに座ると、カカシも隣に腰を下ろす。
いつも通りのにこやかな笑みをイルカはチラと横目で窺った。本当にいつも通り過ぎて、嬉しそうな微笑みを浮かべるカカシ。
でも。
それって、昨日もそんな感じだったんじゃねえか?
「...イルカ先生?」
「あ、はいっ」
カカシの顔を見つめながら思考の波にいたイルカは、引き戻される。
慌てて返事をするとカカシが不思議そうな顔をしていた。
「先生は?」
「...え?」
聞き返すと、カカシは目の前にあるメニューを指さした。
「俺は醤油にするけど、イルカ先生は?」
メニューを聞かれていたのか。全然耳に入っていなかった。メニュー表へ急いで目を向ける。
「えっと...俺は味噌にします」
「じゃあその二つ。お願い」
カカシの注文に店主が元気よく返事をした。
「先生、どうかしたの?」
聞かれてイルカはギクリとした。カカシへ顔を向けると、少し心配そうな目でイルカを見ている。
「いや、別に...どうもしてないですよ」
笑ってカウンターに置かれたグラスを手に取ると水を飲んだ。
それでもカカシはイルカの顔を見つめる。
「何かあった?」
「えっと....」
何かあったって。
(そりゃあ...それは。カカシさんが昨日見たこともない女性と一緒にいて、腕とか組んでたからとか、...って言えるわけないだろうがっ)
口に出来ない言葉を飲み込むとイルカはコップの水をがぶがぶと全部飲み干す。
「イルカ先生?」
「いえ、何でもないですっ」
強く言い切られカカシはまた不思議そうにイルカを窺っている。イルカは気まずそうに唇を噛んだ。
何もやましい事がないからカカシは堂々をしているのだ。だから何も気にする必要なんてない。
それでもちらちら昨日の情景が頭にちらつく。
「おまちっ」
眉を寄せたままのイルカの目の前にラーメンが置かれる。
「いただきますっ」
イルカは手を合わせ言うと、割り箸を取り割って勢いよく食べ始めた。
食べ終わりカカシが会計を済ませようとしてイルカは慌てた。
「いいです。俺が払いますっ」
「いいよ、大丈夫」
カカシは優しく微笑んだ。
いつもだったらいいかな、と思うけど、今日は嫌だった。どうしても払いたい。こんな気持ちのままカカシに奢ってもらっても嬉しくない。
「だったら自分の分だけでも俺払いますからっ」
そう言った時、カカシは、え?、とイルカを見た。
「でも、この前イルカ先生が出したんだよ?だから今度は俺だって、二人で話したじゃない」
そこで思い出す。そう言えばそんな事話したのはつい数日前だった。
「そうでしたね...すみません」
ぺこりと頭を下げた。
「お待たせ」
会計を済ませてるあいだ外で待っていたイルカの横に、カカシがくる。
「ごちそうさまです」
「いいえ」
にこと微笑まれて、イルカも合わせるように微笑んだ。
二人で歩きだしながら、無言のイルカをカカシはしばらく見つめて。そこからひょいと隣からイルカの顔を覗いた。
「イルカ先生。いい加減教えてよ」
どうしたの?
優しい声。
カカシは素直に心配している。
目線を上げれば、その通りで、カカシの心配そうな眼差しをイルカに向けていた。
「変だよ?」
「変ですかね...」
そりゃそうだろうなあ、と力なく微笑みながら答えた。
「だって店でもあんなに水のんじゃって。普段あんなに飲まないじゃない」
気持ちが落ち着かなくて、誤魔化すのもあって飲んでいたのは確か。
でもこれが酒だったらいいのに、と思っていた事にイルカはまた眉を寄せた。
そんな事を思うのは、自分が逃げたいからだ。
そこに気が付きイルカは情けない気持ちになる。
「もー俺恋人なんだよ?言ってくれないなんて寂しいなあ」
カカシは口布の下で口を尖らせたのが分かった。
そうだよな。俺はカカシさんの恋人なんだ。
カカシの口から出た言葉だけで胸が暖かくなり同時に締め付けられる。
「カカシさんっ」
急に立ち止まって名前を呼ばれ、カカシは驚いてイルカを見た。
「うん、...どうしたの?」
勇気を振り絞るように、イルカは握った拳に力を入れた。
「俺、昨日見たんです....その、夕方...商店街で...女性の方と一緒で、」
「え!?」
言い掛けてる時にカカシが驚いた声を上げた。
「昨日って...イルカ先生いたの?」
「ええ...俺買い物で八百屋に」
カカシが驚いた顔をするのは何故だろう。
そこは上忍仲間と約束があって、とか。そんな言葉を想像していたのに。
カカシはそこから眉を寄せた。明らかに困った顔をしている。
あれ、想像してたのと違う。
「...俺に見られたらまずかったって事ですか...」
静かに問うイルカに、カカシはぶんぶんと手と首を振った。
「いや、そうじゃないんだけど。だって、先生に見られるなんて思ってなくて」
「...思ってないなら何ですか」
厳しい目になるイルカに、カカシは困った顔をする。
「違うっ、違うよ?俺はただ仲間に相談してただけで」
「相談?相談だったらまず最初に俺に言ってくれればいいでしょう」
さっきカカシさん恋人だからって、そう言いましたよね。
だんだんと険しい顔になるイルカに、カカシは、参ったな、と呟いて頭を掻いた。
「えっとね。だって...ほらイルカ先生ちゃんと答えてくれなかったから」
ん?と、イルカは首を傾げた。
「答えるって、何をです?」
「ほら、この前。俺聞いたじゃない。バレンタインのお返し何がいいかって」
言われて思い出す。
イルカ先生何か欲しいものってある?
先週の帰り道、カカシにそう聞かれた。
「いえ、何も」
基本物欲がない自分に、すぐに欲しいものはなかった。だから首を振る。
「何でそんな事聞くんですか?」
聞き返すと、カカシは頬を少しだけ赤らめて頭を掻いた。
「え~、だってほら。もうすぐホワイトデーだから」
一瞬イルカはきょとんとして。それから笑い出した。
「え、なに?そこ笑う?」
何で、大事でしょ、と言うカカシを見て笑って。
「俺バレンタインに野菜しか渡してないんですよ?何も貰えませんって」
チョコを改めて渡すのも恥ずかしく、あれから何も渡していないのに。
カカシの律儀なところが妙に可愛く見える。
「あれはイルカ先生の優しさでいただいた報酬なんです。チョコより価値があります」
真面目な顔をされ、イルカはいい加減吹き出した。
「そうですね。でも、欲しいものは何もないですから」
「え、本当に?」
「はい」
きっぱりと言うと、カカシは困った顔をした。
「そっか」
「気持ちだけで十分です」
確か、そんな話だったはずだ。
その会話はちゃんと覚えている。でも。そこから昨日のカカシと何が関係あるのか。
「...確かに、聞かれましたね。でも俺何もいらないって答えましたけど」
胡乱な眼差しで見つめると、カカシはため息を吐き出した。
「そうですが。やっぱ何かあげたいなあって、思って」
「だから仲間に聞いたって事ですか」
少し申し訳なさそうにしているカカシに言えば、小さく頷いた。
「ほら、お菓子詳しい子だったから、色々教えてくれるって言うし」
だから選んでもらったんですよ。
へら、と笑って言う。
「...選んでもらったって...買ったんですか?」
不意の問いに、カカシは一瞬きょとんとして、すぐにまた嬉しそうに頷いた。
「はい、買うって言うか、予約ですが」
カカシの説明(言い訳)に、イルカは明らかに苛立った。
カカシの言っている事は分かる。何もいらないと言われて。でも何かをあげたいと、思ってくれたから。
それでも。それは違う。カカシの自分を思う気持ちに傷ついていると言うのに。
それを分かっていないカカシにも腹が立った。
怒っちゃいけない。カカシは悪気がない。
それは分かっている。
でも。
「どうして...」
イルカは我慢できずに口を開いていた。
「どうして...他の人に選ばせるんですか」
「え?」
「そうでしょう?確かに俺が何か欲しいって伝えなかったのも悪いと思います。だからって、思いつかないからって、他の人に選ばせるなんて。それで俺が喜ぶとでも思ったんですか?」
驚いて目を丸くするカカシはまた、え?と聞き返す。イルカは唇を噛んだ。
「カカシさん俺に言いましたよね?大根でも人参でもブロッコリーでも何でもいいいって。俺からもらえるものなら何でも嬉しいって。それは俺も同じなんですっ。そんな事も分からないんですか?」
荒だった声で言い終わるイルカはカカシを睨む。
カカシは。すごい剣幕のイルカを見つめながら、親に叱られている子供のような顔をした。
「....でも....」
「そうじゃないですか。あんな風に腕を組んで、」
「いや、だって、あれはですね、」
カカシの言葉にイルカは睨んだ。
「でもとかだってとか。言い訳なんて聞きたくないです」
そう言い捨てるとイルカはカカシを置いてアカデミーへ歩き出す。
「イルカ先生、」
「ついてこないでください」
イルカの声に、そこからカカシは何も言わなかった。ついてもこなかった。
その週末はホワイトデーだった。
あれからイルカはカカシを無視している。受付や放課後に顔を見せるが、挨拶だけすると、イルカはそのままカカシが何か言う前に顔を背けていた。
ちょっと、怒りすぎたと思う。
分かっている。
悪気がない。
だからあんなに怒ることはなかったんだ。
ただ、あの時の女といる時の嬉しそうな顔とか。腕を組んでるところとか。忘れなきゃいけない情景ばかり頭に浮かび。それを思い出すとどうしても自分からカカシに声をかけずらかった。
昨日はカカシは姿を見せなかったのは、任務だと、執務室で知った。
それで気が付けば今日はホワイトデー。
イルカは顔を顰めた。ため息を吐き出して立ち上がる。
「イルカ先生もうお帰りですか?」
鞄を肩にかけたとろこで声をかけられる。
「ええ、まあ」
イルカは眉を下げて力なく微笑んだ。
お疲れさまです、と背を向けた女性教員がイルカに振り返った。
「ああ、そうそう。今日はお菓子ありがとうございました」
嬉しそうな彼女の顔を見て、イルカは頭を掻いた。
「いやそんな。あんなものでよかったですかね」
「もちろん。私クッキー好きなんです。また休憩の時にいただきますね」
会釈して去っていくのを見送って。イルカは息を吐き出した。
律儀と言われればそれまでだが。貰ったのに返さない訳にはいかない。
それは、きっとカカシもそうだったに違いない。
分かっている。頭では。
「さてと」
イルカは鞄をしょいなおすと職員室を後にした。
そのままイルカは外に出てそのまま上忍待機所に向かう為に足を向ける。
今日はたぶんそこにいると、調べたから。
だから。こうして早めに上がってカカシに会いに行って。
謝ろう。
でも足取りは重い。
少し俯き廊下を歩きながら、イルカは生徒の声がする窓の外へ顔を向けた。
子供達が嬉しそうに笑いながら歩いている。その楽しそうな姿を眺めた。
(素直じゃねえんだよな、俺は)
無邪気に笑い合う子供達を見ていたら、比べようもないのに自分と子供を重ねて、情けない気持ちになった。
喧嘩したらまず自分から謝れって、生徒に言ってるのに。
(いや、あれは先生が悪いんじゃなくて、俺は謝ろうと思ってるわけで)
誰にでもなく心の中で生徒に言い訳して、イルカは頭を振った。
ぐじぐじしてるなんて俺らしくない。
カカシと出会ってから、見たこともない情けない自分がいる事に気が付かされている。
こんな女々しいなんて。
カカシを好きと思うだけで、胸が痛いくらいに苦しい。
ゆっくり歩いていても上忍待機室まではすぐだった。
扉の外から中を覗くと、見えるのは銀色の髪。
それだけで心臓がが早く打ち出す。とくとく、と高鳴る心臓を抑えるようにベストの上から抑えて。
イルカは扉を開けようとして。カカシが顔を上げた。それはイルカに気が付いたからじゃない。
奥にいた誰かが声をかけたからだ。
そこには見覚えのある若いくノ一。
(また....)
最悪のタイミングにイルカの気持ちがみるみる沈む。
そのくノ一は何か言いながらカカシの腕を急かすように引っ張った。それでもカカシは椅子に座ったまま動かない。断るように手を振る。
何を話しているのか。読唇術をすればいいことなのだが、目の前の二人で頭がいっぱいいっぱいでそこまで頭が回らない。
腕を引っ張られていたカカシが立ち上がった。何か話し始める。
しばらく話して、くノ一が扉に振り返った。
隠れなくてもいいはずなのに。イルカは慌てて身を隠していた。
柱の陰に隠れてすぐ、くノ一は勢いよく部屋から出ていく。見つかったら覗き見をしていたんだと勘違いされてもおかしくはない。自分の存在に気が付かれなかった事に安堵してイルカは息を吐き出した。
そこでイルカは考える。
ーー今度はなんだろう。
少し二人で言い争っていたような感じだった。
何にせよ、見たくないものを見たなあ。
酷く憂鬱な気持ちになる。
でも。
それとこれは別だ。
俺は謝ると決めたんだ。
イルカは意を決するように息を吐き出し。立ち上がる。再び上忍待機室の扉に向かった。
「失礼します」
ノックして扉を開ける。
カカシが驚いて椅子から立ち上がった。
「イルカ先生!」
「こんにちは。今いいですか?」
問いかけると、カカシは先日怒られた時のような顔でイルカを見た。頭をがしがしと掻く。
「あのね、先生。この前の事なんだけど、」
「いえ、カカシさん。先に言わせてください」
言葉を遮るようにして手のひらを見せる。カカシは口を閉じた。
「この前は俺が言い過ぎました。すみません」
深く頭を下げると、カカシが慌てた。
「ちょっと、やめてよ。悪いのは俺です」
「でも言い過ぎた事には変わりありませんから」
だからって、頭上げてよ。ね、イルカ先生。
カカシの手がイルカの肩に乗せられ、そこでイルカはゆっくり頭を戻す。
困った顔でじっとイルカを見つめていた。
「俺も、ごめんね。イルカ先生に言われて。その通りだって思った」
「......」
「イルカ先生が喜ぶかなって、そればっか先に考えて。そしたらそれ以前の問題でしたね」
情けない笑顔を見せて眉を下げる。
イルカは小さく微笑んで首を振った。
「いえ。もうその事はいいんです。...さっきの喧嘩されてた女性も、傷つけてしまったんじゃないですか?」
聞くと、カカシは目を見開いた。
「え?さっきの?先生見てたの?」
イルカは力なく微笑む。
「ええ、丁度見たって言うか、見えてしまって、」
カカシは困ったように眉根を寄せた。
「そうですか」
「で、何を話されていたんですか?」
カカシは、う~ん、と唸ってからイルカに微笑んだ。
「いや、予約してたお菓子。それはもう取りやめて自分で考えようって決めたんです」
「はあ」
「でもそれをさっき言ったら怒っちゃって」
「怒る?」
聞くとカカシは頷いた。
「うん。あれじゃなきゃ絶対駄目だって。もうすごくしつこかったからそんなに欲しいならあげるから取りに行けば、って言ったら、怒って出てっちゃったんです」
「え?」
「え、だから、」
「ちょっとちょっと待ってください」
カカシはイルカの言葉に、ん?と首を傾げた。
「お菓子をその女性に取りに行かせたんですか」
「...はあ」
「はあ、ってそれはカカシさん。あなたが彼女にお願いして選んでもらって、予約したんでしょう?だったら自分で取りに行かないでどうするんですか」
イルカの徐々に帯びる怒りに、カカシは肩を竦めた。
「まあ...そうですけど、...でもね、」
「でもとかだってとか、俺はそんな言葉聞きたくないんですっ」
「ちょーーとまったーーー!!」
バン、と大きな音を立てて扉が開く。
振り返るとさっきのくノ一が肩で息をして立っていた。
「また喧嘩してたんですか?」
驚くイルカに構わず女はそう言うと待機所に入ってくる。
「喧嘩はよくないって言ったじゃないですか」
呆れたような口調でカカシを見ると、カカシは眉を下げて笑った。
「はい、カカシ先生。ちゃんと買ってきました」
手に持っていた包みをカカシに差し出した。
クリーム色の綺麗な包装紙。天使の柄があの新しい洋菓子のイメージとぴったりだった。
ラメの入った綺麗なリボンで包まれている。
これがこの女性が選んだお菓子か。
(.....ん?)
イルカは眉を寄せた。目の前にいる女性を見る。
「今....カカシ先生って、言いました?」
聞くと、そのくノ一は、はい、と素直に頷く。
くノ一がカカシさんを先生?聞いた事がない。
眉を顰めたままのイルカに、
「あ、そっか」
そう呟いて胸の前で印を組んだ。
煙が上がる。
そこには。桜色の髪が見えた。
「さ、サクラっ!」
どこかで見たことがあるとは思ってはいた。でもそれは、サクラが変化の授業中に見せた姿だった。
それを今、ようやく思い出す。そして驚く。
「サクラじゃないか!」
もう一度名前を呼ばれて驚いたままのイルカに頭を下げた。
「先生、こんにちは」
「こ、こんにちはって。お前、...じゃあ、あのこの前カカシさんと一緒にいたのって」
「はい。私です」
サクラがにっこり微笑んで答える。
はあ~、と嘆息してカカシが手を顔に当てた。
「ごめんね。先生。俺が相談したのってサクラだったんですよ」
「ええ!?」
驚きの眼差しはカカシに移る中、カカシは続ける。
「そしたらあそこの店のあのお菓子じゃなきゃ絶対に駄目、とか言われてさ。俺は甘いの苦手でよく分からないし。でもサクラはこの前この店の話をしたら、イルカ先生すごく食べたそうにしてたって言うじゃないですか。だから俺はサクラが言うならそれでいいかなって」
そこまで言うとサクラが腰に手を当てた。
「それなのに、カカシ先生。あんな店恥ずかしいから一人で買いに行けない、なんて言うんですよ?一緒に行くって言っても部下とは行きたくないとか言うし。信じられないったらないんだから」
だから私が一肌脱いだんです。全くしっかりして欲しいわ。
そう言うサクラは、丸でしっかりしたお母さんのような口調になっている。
カカシはまた笑って頭を掻いた。
それなのに、と、そこからサクラは呆けた顔になっているイルカに顔を向けた。
「イルカ先生と喧嘩しちゃったからもうそこのお菓子はいらないって、それって酷くないですか?」
もう。喧嘩なんて、やめてください。
強い口調に、イルカは、はい、と返事をする。
「ここのお菓子雑誌にも載ってお墨付きの美味しさなんです。絶対食べてくださいね」
「わ、分かった」
イルカが頷くと、サクラは満足したように息を吐き出した。
「じゃあ私はもう帰ります。もしかしたらサスケくんお返しくれるかもしれないしっ」
そこで初めて子供の表情に戻り、頬を赤らめる。頭を下げサクラは部屋から出ていった。
どうかね~、とカカシが呟いたのはサクラの気配がなくなった後だった。
上忍待機室に残された二人。
イルカはゆっくりと椅子に座って頭を抱えた。
今さっき過ぎ去った事を再生し。それだけで顔が赤くなる。同時に消えてしまいたい気持ちになる。
カカシは部下の気持ちを汲んでいただけで。しかも俺はその相手に嫉妬して。しかもそれがサクラで。
しかも。サクラがカカシと自分の関係を知って。
「...イルカ先生?」
イルカの隣に座ったカカシに、がばっと顔を上げる。
「何でサクラに言ったんですか!?」
泣きそうな顔のイルカにカカシは眉を下げて微笑んだ。
「言ってないですよ。ただ、イルカ先生は何が好きかって、ちょっと聞いただけなんです」
だって、サクラはイルカ先生の教え子でしょ?
「...はい...」
ふくれたままの顔で小さく答えるとカカシはにこっと笑みを浮かべた。
「ナルトだけじゃない。サクラだっていつも俺にあなたの事を話してくれるんですよ。だから、きっといいアドバイスくれるって、俺はそう思ったんです。まあ、結果的にごり押しで決められちゃいましたけど」
そこでまたカカシが笑った。
だから決して他人に選ばせるつもりはなかったんです。
イルカはむくれたままその話を聞いて。
アカデミーから巣立った生徒と、その新しい担当になった上忍師のカカシの気持ちを知って。嬉しくないわけがない。
「....分かりました」
頬を赤らめて呟いた。
結局サクラにばれたからって、カカシを嫌いになる訳がないんだから。
この人が好きだ。
それは隠さない。
カカシが口布を下げ顔が近づく。
それがどんな意味か。
イルカは薄く口を開いてカカシの唇を受け止めた。
触れては離れ、何度もそれを繰り返す。
それだけで心が満たされていく。
(...初めてのキスが上忍待機室か...)
甘いムードに流されながら、イルカはカカシの首に腕を回した。深く口づける。
その横に置かれた可愛いお菓子の箱。
中身はマカロン。ーー特別な人。
その意味を知っているのはサクラだけ。
スキップして帰りながら、秘かにガッツポーズしたサクラを、二人は知らない。
<終>
拍手ボタンを4/3に撤去いたしました。
Sponsored link
This advertisement is displayed when there is no update for a certain period of time.
It will return to non-display when content update is done.
Also, it will always be hidden when becoming a premium user.