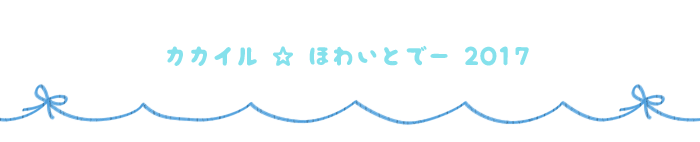雲「マロングラッセ ~永遠の愛を誓う証~」
マロングラッセとは栗を砂糖漬けにした菓子のことだ。 殻をむいた栗をシロップで煮て、日にちをかけて徐々に糖度をあげていく。
昔、異国の王が最愛の妻に作ったことから、永遠の愛を誓う証として贈るらしい。
そんなこと、調べて初めて知った。
(・・・・・・ふーん)
他にもクッキーはサクッとした食感であることから「軽い関係=友達」という意味らしいし、マシュマロはすぐに溶けてなくなってしまうので「あなたが嫌い」という意味を含んでいるらしい。無理矢理感が拭えない。
その割にはホワイトデーのブースにはマロングラッセに比べて堂々と並んでいるところをみると全然浸透していないのか、わざわざ意味を調べて口にできない思いを物に託しているのか。ホワイトデーとは本当に奇妙な行事だ。
コトコトと煮詰める栗を見て、甘い匂いに眉を顰める。
甘いものは苦手だ。
それを美味いと感じる味覚は捨てた。甘さと甘えは同じようで、だからこそ自分には不似合いだから早々に切り捨てたのだ。
だけど。
あの人を想うと昔食べた甘い菓子のような感覚になる。
甘くて、綺麗で、見ているだけで胸が高鳴るような、幸せな感覚と。
カチッと火を止める。今日分の煮詰める時間は終わりだ。また明日、砂糖を足して煮詰めなければならない。
毎日少しずつ、少しずつ甘さを足していく。そして甘い蜜の中でゆっくりと馴染ませ、柔らかくし、甘くする。
それはまるで恋のようだ。
なんでこんなもの作っているのかと言うと、単に恋人にバレンタインデーのお返しをあげるためだ。
今までそんなもの人にあげたことがなかったので、何をあげていいか分からず、ひたすら調べた。バレンタインデーはチョコをあげればいいと決まっているのに、ホワイトデーは決まっていない。だからこそ古今東西ありとあらゆるものを調べて行き着いたのがマロングラッセだった。
時間をかけて作らなければならないことや、それに込められた意味など傍から見ればこんなに重いものはないだろう。
相手が知ればゾッとするのは容易に分かってた。
だけどこれを選ばすにはいられなかった。
重くて。
手間がかかって。
そして、甘い。
これ以上、オレの感情に似合いのものはないから。
きっかけは色々あったが、この恋に理解した時浮かんだのが「厄介な人好きになったなぁ」ということだった。
性別や階級は勿論、よくよく観察するとこの人人の好意に深く距離を置いていることに気がついた。
もう少し近づけばきっと恋に発展できそうな場面で、彼はあからさまに遠回りをして近づかなかった。好意が消えるとある程度の距離を保って近づく。それを嘆いていないので意図的であることは明白だった。彼は人と深く関わろうとはしないのだとはっきりと理解した。
きっと。
きっと今、オレがいくら言葉を尽くして告白しても、告白したその事実だけで拒否されるだろう。
人間性など一切見ずに。
好意を受け入れないというだけで。
そんな振られ方で誰が納得するか。
振られるなら振られるだけ、この想いに返せるだけの彼の想いが欲しい。
オレが好きか嫌いか、判断してほしい。
せめて人間性を見て選んでくれ。
この狂おしい想いを知ってくれ。
簡単に、オレの想いを切り捨てないでくれ。
やけにムキになったのは最初だけだった。
そうやって意地になって追いかければ追いかけるだけ、彼は離れていくし、オレはズブズブと深みにハマっていった。
段々と距離が離れていく歯がゆさで、意地でもこちらに意識させようと、やけに必死に彼を構った気がする。こっちはなりふり構わずにやっていたが、後から彼に聞いたら「確かに意識したが、ベクトルは逆にいった」なんて言うのだから努力は報われないと思う。
それが一ヶ月前に一転したのだ。
バレンタインデーとかいうチョコレート会社の策略によって。
あの日、いつもの様に受付にいる彼に会いに行って言葉を交わした。
ころころ表情が変わって面白いなぁと眺めていたら段々と不機嫌そうな顔になっていった。
最近、彼と話すと何故か段々と不機嫌そうな顔になる。こちらは必死に言葉を繋いでいるのに何が不満だと言うのだろうか。
そういう顔をされるとこちらもムキになって、それでも言葉を紡ぎ出してもらおうと躍起になる。オレは話したいだけなのに。混んでいる訳では無いのだから少しぐらい話をしたっていいではないか。どんどん険しくなってく顔に焦りと少しの憤りを感じながらそれでも話かけていると、ふとある物が視界に入った。
それはありふれたチョコレートだった。
瞬時にそれが何の物か、分かった。
今日がなんの日で。
それがなんの意味を持って。
どうしてここに溢れているのか。
どうせあの計算高い姫のことだ。ここらで好感度でもあげようとでも思ったのか、お返しと称して働かせるか。そんな思惑があるチョコレートを、この誰からも好かれるような人に配らせて任務前にやる気を出させるのだろう。全く人の好意も善意も上手く混ぜ合わせた思惑だ。
ここで待ってたら、彼はくれるだろう。
他の人と同じように、火影様からですと笑いながら。
好意の象徴を、善意の塊に代えて。
オレがずっと欲しかったものを、アンタはまた姿を変えて、目を背けて、押し付けるのだ。
オレの気持ちなど見向きもしないで。
そんなもの、誰がいるか。
溢れ出そうな殺気を押しとどめて、さっさとその場を後にする。そうでないとあの塊を燃やしかねなかった。
歩きながら報われないなぁと思った。
努力すれば報われるということは、恋愛に関しては必ずしもそうではないと思う。
オレが興味のない人から好意をいくらもらってもなんとも思わないと同じように、いくらオレが努力したってその分だけ好いてくれるわけではない。無理だと思われれば先に進むことは無い。
報われないこの恋の終着点は、諦めることなのだろうか。
ありふれた、よくある話のように。
「はたけ上忍!」
後ろから声がした。
それを期待と、不安がごちゃ混ぜになった感情を押し込んで振り向く。
良いか、悪いか、二つに一つだ。
さっきのチョコレートをただただ持ってきただけかもしれない。
だけど、もしかしたら。
もしかしたら、彼はオレだけに用意してくれたのかもしれない。理由はなんでもいい。ナルトの上忍師だからとかそんな理由でもいい。
そんな理由でいいから、オレを見てくれ。
その他大勢と、一緒にしないでくれ。
「その・・・、これを・・・」
そう言って手渡されたのは。
あの、ありふれたチョコレート。
馬鹿にしやがって。
馬鹿にしやがって・・・っ。
アンタはこれを渡された人の気持ちを少しでも考えたことあるのか。
善意の塊は時として何よりの凶器となることを、アンタは知らないのか。
相手にはその気がなくても、これがズカズカと心の中に居座ることを知らないのか。
本当に好きな人からもらったこのありふれたチョコレートが。
チョコレートが。
こんなにも愛おしく思えるのを、知らないくせに。
あぁ、嫌だな。
なんでこんなもの。
こんなもの、こんなに嬉しいんだろう。
顔が蕩けていくのがよく分かった。
止めれなかった。
止めたくなかった。
嬉しい。
凄く嬉しい。
なんだか目を閉じたら。
色んなごちゃごちゃしたことを、見ないふりしたら。
まるで本物みたいだ。
「嬉しい」
嬉しくてたまらない。
こんなありふれて気持ちのこもっていないチョコレートでも。
アンタから貰えた事実さえあれば。
こんなにも嬉しい。
「ねぇ、これオレに?アンタから?」
「あ、えっと・・・」
「嬉しいなぁ。ありがと。大切にする」
思わず矢継ぎ早に話しかけるといつものように不機嫌そうな顔をしなかった。それに調子に乗ってどんどん喋る。
「ね、この後暇?お礼にさ、夕飯奢るよ」
「え?」
「ねぇ、行こ。いいとこ知ってるから」
「あの、でも・・・・・・」
「ね、ほら、約束したでしょ?」
もうずっと前。
まだアンタと上手く喋れてて、オレをきちんと一人の人間として見てくれていた頃の約束。
ずっと、いつかいつかと思っていた約束。
嬉しさを隠せない顔でそう言うと、彼はぎゅっと眉を寄せて。
だけどしっかり頷いてくれた。
頷いてくれたのだ。
彼の中に常にあった誰も深くまで寄せ付けなかった強固な殻が。
小さく、だけど確かに壊れていくのを感じた。
「あ、の・・・っ、もう少しで、終わりますから・・・。お待たせするかも知れないのですが」
「いいよ、大丈夫。先に行って予約してくるから。式送るね」
「はい」
また、確かに頷いてくれた。
きっと、彼は来てくれるだろう。
オレに会うために。
思わず身震いする。
歓喜が体から溢れでる。
あぁ、もう最高だ。
こんなチョコレートひとつで、彼の内側に入り込めたのだ。
ならばあとは心の中にドロドロに溶けて浸透するだけだ。
■■■
「はいコレ」
とんっと置かれたのは塩辛と書いてあるビンだった。
塩辛、確かに好物だ。これを酒のつまみにすればキュッとやれる。
「ありが」
「ホワイトデーだから」
ホワイトデー?
そう言われて差し出された報告書日付を見る。
三月十四日。
あれから一ヶ月たったのだ。
あぁ、ホワイトデーってお返しの日か。
まぁあげたしな。この人に。チョコレートを。
「ありがとうございます?」
お返しの日って何あげてもよかったんだっけ?
塩辛、好きだけど。
なんかもっとこう、ぽっぷだった気が・・・。
いやほっぷ?
まぁいっか。塩辛好きだから。
「これつまみに一杯やります?」
そう言うと、とても微妙な顔された。
「酒のつまみ・・・?」
「えぇ、これ焼酎と合うんですよ」
よく見ると高級で旨いと専ら有名な老舗屋さんの塩辛だ。
食べてみたかったんだよなぁ。
男同士で付き合うなんて考えたこともなかったけど、こうやって食べ物の趣味も合うし、気取らなくていいから楽だなぁ。
ニコニコ笑っていると、「まぁいいけど」と頷いてくれた。
「で、報告書は?」
「あっ、ちょっ、待ってください!」
「アンタ本当とろいねぇ」
アンタが別の話ふってきたからだろ!
相変わらずムカつくなと思いながらもミスをしないようにしっかり確認する。
「・・・はい、大丈夫です」
「終わったらウチ来な。惣菜買っとくから。焼酎は前の残りでいい?」
「はい!あ、前作ってくれた味噌汁食べたいです」
「お吸い物ね。ハイハイ作っとくよ」
そう言って去っていくと、隣にいた同僚が驚いた顔していた。
「お前、なんていうか色々すげーな」
「ん?カカシさんと付き合ってること?」
「それと部屋に行き来してることと料理作らすこともだよ」
「そーだなぁー」
この一ヶ月よく言われた言葉だった。
だがあちらから付き合って欲しいと言われたし、部屋だってあちらから招いてくれるし、料理だってあちらが作ってくれるのだ。俺がおかしいみたいな言い方ばかりされてなんだか不公平だと感じる。相手が色んな意味で有名なのは知っているが、普通に平凡なお付き合いをしているだけで異様なように言われるのは心外だ。
「はたけ上忍と言えば、付き合う女は日替わり、プライベートには一切寄せ付けず、尽すなんて有り得ない人だぞ」
「んな大袈裟な」
「それが、ホワイトデーでお返し?有り得ない」
「部外者なのにヒドイ言われようだなぁ。あの人本当にろくでもない生活してたのか」
「もう次元の違う人だよ。そんな人に尽くされて。はぁー・・・、イルカ愛されてるなぁ」
そう言われて、どう答えていいか分からず曖昧に笑った。
「それよりもそれ、何だよ」
そう言って塩辛を指した。
「え?塩辛だろ?」
だが、よくよく見ると中身が全く異なっていた。
木の実のような、ホルマリン漬けにされた脳のようなモノがしきつめられている。
「・・・・・・なんだこれ?」
瓶をあけてみると甘い香りが立ち込めた。
ペロッと周りの液体を舐めてみると蜜のような甘い味がした。
「あーあーあー!」
見たことがある菓子だった。同僚も同じことを思ったのか顔を顰めて必死で思い出そうとしている。
「えーっと、なんて言ったっけ・・・?」
「確かー・・・、横文字で、栗が何とか・・・」
「栗じゃなくて・・・えーっと・・・」
「ロマングリップ!」
「違うけど遠くない!」
「あら、マロングラッセ?」
綺麗な声がすると思ったら正面に紅先生が物珍しそうにこちらを眺めていた。
「あ、すみません。報告書預かります」
「いいのよ。今誰もいないじゃない」
そう言って妖艶に笑う。
こんな美人で性格もいいなんて、本当アスマ兄は羨ましい。
「カカシから?マロングラッセ作るって騒いでたけど本当に作ったのねぇ」
「マロングラッセってどうやって作るのですか?」
「栗の皮むいて、砂糖で煮るの」
「へぇ」
「でもねぇ、何日も煮詰めなきゃいけないし、結構面倒なのよ。栗だって季節外れだし」
そう言われると、塩辛のビンが何だか重みが増した気がした。
塩辛のビンというのが彼らしい。ラッピングとかそういう考えはないのだろう。だけどわざわざ作ったのだ。手間のかかる菓子を。
「別に俺、栗そんなに好きじゃないんだけど・・・」
「何か意味があるのかもね。顔に似合わずロマンチックだから」
ロマンチック・・・。
ロマンとマロンをかけたのだろうか。
そんな洒落っ気な人だったっけ?
んー?と考えてると紅先生がニコリと笑った。
「愛されてるわね」
まったく。
有名で、普段何もしない人が、ちょっと何か人のためにすると、ワイワイと持て囃される。きっと俺がしたら「なに気合い入れてるんだよ」と笑われるだけなのに。
でも。
商店街の八百屋にも。
近所のスーパーにも。
栗なんて勿論、売ってなかった。
どのぐらい前から準備していたのだろう。
どれぐらい前から考えていたのだろう。
そうやって、手間暇かけて気持ちを返されることは。
それが特別だって。
アンタが特別だって。
目に見えて証明してくれるようだった。
「早かったね」
部屋に入ると寛いだ格好で出迎えてくれた。ニコリと笑った顔はどこか機嫌が良さそうだった。
カカシさんが里にいる時は、この部屋か俺の部屋かどちらかでよく会った。外食する時もあったけど、気兼ねなく長居できるからと部屋の方が多い。メシだって惣菜でいいし、酒は好き勝手飲めるし、同世代だから話は合うし。
一緒にいて、本当に苦じゃない。
それはまるで友人のようで、男同士の付き合いなんてそんなものだと思っていた。
だけど。
俺は無言で台所に行く。
鍋をみるとお吸い物しかなくて、どれだけ準備したのか、本当に彼が作ったのか、その跡は一つも残っていなかった。
だけど、そう言えばここ数日彼の部屋に招いてはくれなかった。会うこともほとんど無かったし、夕食に誘われることもなかった。
それを悲しいでもなく寂しいでもなく、腹立たしく感じた俺は、変だった。
そんなこと友人に感じたことなかったのに。
彼のこと友人の延長にしか思ってなかったのに。
悪い噂ばかり飛び交う彼が、尽くしてくれるのを見て。
誰でもない周りがざわめきだすのを見て、優越感に浸る俺は、やっぱり変だ。
「何?どうしたの?」
「・・・・・・いえ、本当にマロングラッセ作ったのかなぁと思って」
「はぁ?作ったけど?」
「手間がかかるって聞きました」
「そーね。でも作れないものじゃないし」
「栗だって別に好きじゃないし」
「だろうね」
「じゃあなんで」
そう聞くと、にこぉっと嬉しそうに笑った。
その顔は一ヶ月前に見た顔だった。
そして。
「似合うなぁと思って」
そして、ここ一ヶ月よく見る顔だった。
俺も顔を上げて彼の方を見た。
「嬉しいです」
うまく笑えているだろうか。
彼のように幸せそうに笑っているだろうか。
「大事にします」
ぎゅっと彼を抱きしめた。
ずっと、誰かの特別になりたかった。
だけどその他大勢で、選ばれることなく、それが嫌で、怖くて、誰にも近づかなかった。
特別なんて、どうやったらなるのか、どうやったらなれるのか分からなかったけど。
今が特別だって、確かに分かる。
「俺、カカシさん大好きです」
「単純だねぇ、アンタ」
「カカシさんほどじゃないです」
この人チョコレート貰ったぐらいで惚れたくせに。
そう思ったが、言ってやらない。
「カカシさん。俺のも腐らない術かけてください」
「はぁ?そんなものないよ」
「俺があげたチョコ流しの下に隠してるくせに」
俺があげた、チョコレートが二つとも。
そう言うとバツが悪そうにした。
それが可笑しくて笑うと力いっぱい抱きしめられた。
「いたたたたっ」
「アレはいーの。アンタのは欲しかったら何時でも作ってあげるよ」
「俺のだっていつだって買ったあげますよ!」
全く手をつけず、大事に隠されているチョコレート。きっと食べることなく、飾られていくのだろう。
アンタがほしいなら、いつだって、いくらだってあげるのに。
カカシさんはひどく驚いた顔をして、俺の肩に頭を置いた。
「くれるつもりなんてなかったクセに・・・」
「え?何ですか?」
小さくて聞き取れなかった。もう一回言って欲しかったのに、彼はグリグリと頭を押し付けるだけだった。
「じゃあ来年もね」
そんな当たり前のこと言って、馬鹿だなぁと思った。
「来年は俺、作りますよ!すっごいの!」
彼に負けないような凄いのを作って知らしめてやりたい。
俺だって彼が好きなことを。特別だってことを。
周りにも。
彼自身にも。
「ふぅん」
「その前に誕生日ですかね?ケーキ作りましょうか!」
「イルカ先生」
肩口から見上げるように俺を見た。色の違う目がこちらを見ている。
甘くてドロリとした目で。
「キスしたい」
それは彼が初めて口にした色の含んだセリフだった。
キスは特別な人に。
愛をこめて相手に触れる特別なコト。
そんなこと当たり前のように浮かぶのだから。
この人は特別なのだと思う。
「俺はずっと思ってましたよ!」
そう言って笑うと、またにこぉっと嬉しそうに笑ってくれた。
そして目を閉じた顔がゆっくり近づいてきた。
<終>
拍手ボタンを4/3に撤去いたしました。
昔、異国の王が最愛の妻に作ったことから、永遠の愛を誓う証として贈るらしい。
そんなこと、調べて初めて知った。
(・・・・・・ふーん)
他にもクッキーはサクッとした食感であることから「軽い関係=友達」という意味らしいし、マシュマロはすぐに溶けてなくなってしまうので「あなたが嫌い」という意味を含んでいるらしい。無理矢理感が拭えない。
その割にはホワイトデーのブースにはマロングラッセに比べて堂々と並んでいるところをみると全然浸透していないのか、わざわざ意味を調べて口にできない思いを物に託しているのか。ホワイトデーとは本当に奇妙な行事だ。
コトコトと煮詰める栗を見て、甘い匂いに眉を顰める。
甘いものは苦手だ。
それを美味いと感じる味覚は捨てた。甘さと甘えは同じようで、だからこそ自分には不似合いだから早々に切り捨てたのだ。
だけど。
あの人を想うと昔食べた甘い菓子のような感覚になる。
甘くて、綺麗で、見ているだけで胸が高鳴るような、幸せな感覚と。
カチッと火を止める。今日分の煮詰める時間は終わりだ。また明日、砂糖を足して煮詰めなければならない。
毎日少しずつ、少しずつ甘さを足していく。そして甘い蜜の中でゆっくりと馴染ませ、柔らかくし、甘くする。
それはまるで恋のようだ。
なんでこんなもの作っているのかと言うと、単に恋人にバレンタインデーのお返しをあげるためだ。
今までそんなもの人にあげたことがなかったので、何をあげていいか分からず、ひたすら調べた。バレンタインデーはチョコをあげればいいと決まっているのに、ホワイトデーは決まっていない。だからこそ古今東西ありとあらゆるものを調べて行き着いたのがマロングラッセだった。
時間をかけて作らなければならないことや、それに込められた意味など傍から見ればこんなに重いものはないだろう。
相手が知ればゾッとするのは容易に分かってた。
だけどこれを選ばすにはいられなかった。
重くて。
手間がかかって。
そして、甘い。
これ以上、オレの感情に似合いのものはないから。
きっかけは色々あったが、この恋に理解した時浮かんだのが「厄介な人好きになったなぁ」ということだった。
性別や階級は勿論、よくよく観察するとこの人人の好意に深く距離を置いていることに気がついた。
もう少し近づけばきっと恋に発展できそうな場面で、彼はあからさまに遠回りをして近づかなかった。好意が消えるとある程度の距離を保って近づく。それを嘆いていないので意図的であることは明白だった。彼は人と深く関わろうとはしないのだとはっきりと理解した。
きっと。
きっと今、オレがいくら言葉を尽くして告白しても、告白したその事実だけで拒否されるだろう。
人間性など一切見ずに。
好意を受け入れないというだけで。
そんな振られ方で誰が納得するか。
振られるなら振られるだけ、この想いに返せるだけの彼の想いが欲しい。
オレが好きか嫌いか、判断してほしい。
せめて人間性を見て選んでくれ。
この狂おしい想いを知ってくれ。
簡単に、オレの想いを切り捨てないでくれ。
やけにムキになったのは最初だけだった。
そうやって意地になって追いかければ追いかけるだけ、彼は離れていくし、オレはズブズブと深みにハマっていった。
段々と距離が離れていく歯がゆさで、意地でもこちらに意識させようと、やけに必死に彼を構った気がする。こっちはなりふり構わずにやっていたが、後から彼に聞いたら「確かに意識したが、ベクトルは逆にいった」なんて言うのだから努力は報われないと思う。
それが一ヶ月前に一転したのだ。
バレンタインデーとかいうチョコレート会社の策略によって。
あの日、いつもの様に受付にいる彼に会いに行って言葉を交わした。
ころころ表情が変わって面白いなぁと眺めていたら段々と不機嫌そうな顔になっていった。
最近、彼と話すと何故か段々と不機嫌そうな顔になる。こちらは必死に言葉を繋いでいるのに何が不満だと言うのだろうか。
そういう顔をされるとこちらもムキになって、それでも言葉を紡ぎ出してもらおうと躍起になる。オレは話したいだけなのに。混んでいる訳では無いのだから少しぐらい話をしたっていいではないか。どんどん険しくなってく顔に焦りと少しの憤りを感じながらそれでも話かけていると、ふとある物が視界に入った。
それはありふれたチョコレートだった。
瞬時にそれが何の物か、分かった。
今日がなんの日で。
それがなんの意味を持って。
どうしてここに溢れているのか。
どうせあの計算高い姫のことだ。ここらで好感度でもあげようとでも思ったのか、お返しと称して働かせるか。そんな思惑があるチョコレートを、この誰からも好かれるような人に配らせて任務前にやる気を出させるのだろう。全く人の好意も善意も上手く混ぜ合わせた思惑だ。
ここで待ってたら、彼はくれるだろう。
他の人と同じように、火影様からですと笑いながら。
好意の象徴を、善意の塊に代えて。
オレがずっと欲しかったものを、アンタはまた姿を変えて、目を背けて、押し付けるのだ。
オレの気持ちなど見向きもしないで。
そんなもの、誰がいるか。
溢れ出そうな殺気を押しとどめて、さっさとその場を後にする。そうでないとあの塊を燃やしかねなかった。
歩きながら報われないなぁと思った。
努力すれば報われるということは、恋愛に関しては必ずしもそうではないと思う。
オレが興味のない人から好意をいくらもらってもなんとも思わないと同じように、いくらオレが努力したってその分だけ好いてくれるわけではない。無理だと思われれば先に進むことは無い。
報われないこの恋の終着点は、諦めることなのだろうか。
ありふれた、よくある話のように。
「はたけ上忍!」
後ろから声がした。
それを期待と、不安がごちゃ混ぜになった感情を押し込んで振り向く。
良いか、悪いか、二つに一つだ。
さっきのチョコレートをただただ持ってきただけかもしれない。
だけど、もしかしたら。
もしかしたら、彼はオレだけに用意してくれたのかもしれない。理由はなんでもいい。ナルトの上忍師だからとかそんな理由でもいい。
そんな理由でいいから、オレを見てくれ。
その他大勢と、一緒にしないでくれ。
「その・・・、これを・・・」
そう言って手渡されたのは。
あの、ありふれたチョコレート。
馬鹿にしやがって。
馬鹿にしやがって・・・っ。
アンタはこれを渡された人の気持ちを少しでも考えたことあるのか。
善意の塊は時として何よりの凶器となることを、アンタは知らないのか。
相手にはその気がなくても、これがズカズカと心の中に居座ることを知らないのか。
本当に好きな人からもらったこのありふれたチョコレートが。
チョコレートが。
こんなにも愛おしく思えるのを、知らないくせに。
あぁ、嫌だな。
なんでこんなもの。
こんなもの、こんなに嬉しいんだろう。
顔が蕩けていくのがよく分かった。
止めれなかった。
止めたくなかった。
嬉しい。
凄く嬉しい。
なんだか目を閉じたら。
色んなごちゃごちゃしたことを、見ないふりしたら。
まるで本物みたいだ。
「嬉しい」
嬉しくてたまらない。
こんなありふれて気持ちのこもっていないチョコレートでも。
アンタから貰えた事実さえあれば。
こんなにも嬉しい。
「ねぇ、これオレに?アンタから?」
「あ、えっと・・・」
「嬉しいなぁ。ありがと。大切にする」
思わず矢継ぎ早に話しかけるといつものように不機嫌そうな顔をしなかった。それに調子に乗ってどんどん喋る。
「ね、この後暇?お礼にさ、夕飯奢るよ」
「え?」
「ねぇ、行こ。いいとこ知ってるから」
「あの、でも・・・・・・」
「ね、ほら、約束したでしょ?」
もうずっと前。
まだアンタと上手く喋れてて、オレをきちんと一人の人間として見てくれていた頃の約束。
ずっと、いつかいつかと思っていた約束。
嬉しさを隠せない顔でそう言うと、彼はぎゅっと眉を寄せて。
だけどしっかり頷いてくれた。
頷いてくれたのだ。
彼の中に常にあった誰も深くまで寄せ付けなかった強固な殻が。
小さく、だけど確かに壊れていくのを感じた。
「あ、の・・・っ、もう少しで、終わりますから・・・。お待たせするかも知れないのですが」
「いいよ、大丈夫。先に行って予約してくるから。式送るね」
「はい」
また、確かに頷いてくれた。
きっと、彼は来てくれるだろう。
オレに会うために。
思わず身震いする。
歓喜が体から溢れでる。
あぁ、もう最高だ。
こんなチョコレートひとつで、彼の内側に入り込めたのだ。
ならばあとは心の中にドロドロに溶けて浸透するだけだ。
■■■
「はいコレ」
とんっと置かれたのは塩辛と書いてあるビンだった。
塩辛、確かに好物だ。これを酒のつまみにすればキュッとやれる。
「ありが」
「ホワイトデーだから」
ホワイトデー?
そう言われて差し出された報告書日付を見る。
三月十四日。
あれから一ヶ月たったのだ。
あぁ、ホワイトデーってお返しの日か。
まぁあげたしな。この人に。チョコレートを。
「ありがとうございます?」
お返しの日って何あげてもよかったんだっけ?
塩辛、好きだけど。
なんかもっとこう、ぽっぷだった気が・・・。
いやほっぷ?
まぁいっか。塩辛好きだから。
「これつまみに一杯やります?」
そう言うと、とても微妙な顔された。
「酒のつまみ・・・?」
「えぇ、これ焼酎と合うんですよ」
よく見ると高級で旨いと専ら有名な老舗屋さんの塩辛だ。
食べてみたかったんだよなぁ。
男同士で付き合うなんて考えたこともなかったけど、こうやって食べ物の趣味も合うし、気取らなくていいから楽だなぁ。
ニコニコ笑っていると、「まぁいいけど」と頷いてくれた。
「で、報告書は?」
「あっ、ちょっ、待ってください!」
「アンタ本当とろいねぇ」
アンタが別の話ふってきたからだろ!
相変わらずムカつくなと思いながらもミスをしないようにしっかり確認する。
「・・・はい、大丈夫です」
「終わったらウチ来な。惣菜買っとくから。焼酎は前の残りでいい?」
「はい!あ、前作ってくれた味噌汁食べたいです」
「お吸い物ね。ハイハイ作っとくよ」
そう言って去っていくと、隣にいた同僚が驚いた顔していた。
「お前、なんていうか色々すげーな」
「ん?カカシさんと付き合ってること?」
「それと部屋に行き来してることと料理作らすこともだよ」
「そーだなぁー」
この一ヶ月よく言われた言葉だった。
だがあちらから付き合って欲しいと言われたし、部屋だってあちらから招いてくれるし、料理だってあちらが作ってくれるのだ。俺がおかしいみたいな言い方ばかりされてなんだか不公平だと感じる。相手が色んな意味で有名なのは知っているが、普通に平凡なお付き合いをしているだけで異様なように言われるのは心外だ。
「はたけ上忍と言えば、付き合う女は日替わり、プライベートには一切寄せ付けず、尽すなんて有り得ない人だぞ」
「んな大袈裟な」
「それが、ホワイトデーでお返し?有り得ない」
「部外者なのにヒドイ言われようだなぁ。あの人本当にろくでもない生活してたのか」
「もう次元の違う人だよ。そんな人に尽くされて。はぁー・・・、イルカ愛されてるなぁ」
そう言われて、どう答えていいか分からず曖昧に笑った。
「それよりもそれ、何だよ」
そう言って塩辛を指した。
「え?塩辛だろ?」
だが、よくよく見ると中身が全く異なっていた。
木の実のような、ホルマリン漬けにされた脳のようなモノがしきつめられている。
「・・・・・・なんだこれ?」
瓶をあけてみると甘い香りが立ち込めた。
ペロッと周りの液体を舐めてみると蜜のような甘い味がした。
「あーあーあー!」
見たことがある菓子だった。同僚も同じことを思ったのか顔を顰めて必死で思い出そうとしている。
「えーっと、なんて言ったっけ・・・?」
「確かー・・・、横文字で、栗が何とか・・・」
「栗じゃなくて・・・えーっと・・・」
「ロマングリップ!」
「違うけど遠くない!」
「あら、マロングラッセ?」
綺麗な声がすると思ったら正面に紅先生が物珍しそうにこちらを眺めていた。
「あ、すみません。報告書預かります」
「いいのよ。今誰もいないじゃない」
そう言って妖艶に笑う。
こんな美人で性格もいいなんて、本当アスマ兄は羨ましい。
「カカシから?マロングラッセ作るって騒いでたけど本当に作ったのねぇ」
「マロングラッセってどうやって作るのですか?」
「栗の皮むいて、砂糖で煮るの」
「へぇ」
「でもねぇ、何日も煮詰めなきゃいけないし、結構面倒なのよ。栗だって季節外れだし」
そう言われると、塩辛のビンが何だか重みが増した気がした。
塩辛のビンというのが彼らしい。ラッピングとかそういう考えはないのだろう。だけどわざわざ作ったのだ。手間のかかる菓子を。
「別に俺、栗そんなに好きじゃないんだけど・・・」
「何か意味があるのかもね。顔に似合わずロマンチックだから」
ロマンチック・・・。
ロマンとマロンをかけたのだろうか。
そんな洒落っ気な人だったっけ?
んー?と考えてると紅先生がニコリと笑った。
「愛されてるわね」
まったく。
有名で、普段何もしない人が、ちょっと何か人のためにすると、ワイワイと持て囃される。きっと俺がしたら「なに気合い入れてるんだよ」と笑われるだけなのに。
でも。
商店街の八百屋にも。
近所のスーパーにも。
栗なんて勿論、売ってなかった。
どのぐらい前から準備していたのだろう。
どれぐらい前から考えていたのだろう。
そうやって、手間暇かけて気持ちを返されることは。
それが特別だって。
アンタが特別だって。
目に見えて証明してくれるようだった。
「早かったね」
部屋に入ると寛いだ格好で出迎えてくれた。ニコリと笑った顔はどこか機嫌が良さそうだった。
カカシさんが里にいる時は、この部屋か俺の部屋かどちらかでよく会った。外食する時もあったけど、気兼ねなく長居できるからと部屋の方が多い。メシだって惣菜でいいし、酒は好き勝手飲めるし、同世代だから話は合うし。
一緒にいて、本当に苦じゃない。
それはまるで友人のようで、男同士の付き合いなんてそんなものだと思っていた。
だけど。
俺は無言で台所に行く。
鍋をみるとお吸い物しかなくて、どれだけ準備したのか、本当に彼が作ったのか、その跡は一つも残っていなかった。
だけど、そう言えばここ数日彼の部屋に招いてはくれなかった。会うこともほとんど無かったし、夕食に誘われることもなかった。
それを悲しいでもなく寂しいでもなく、腹立たしく感じた俺は、変だった。
そんなこと友人に感じたことなかったのに。
彼のこと友人の延長にしか思ってなかったのに。
悪い噂ばかり飛び交う彼が、尽くしてくれるのを見て。
誰でもない周りがざわめきだすのを見て、優越感に浸る俺は、やっぱり変だ。
「何?どうしたの?」
「・・・・・・いえ、本当にマロングラッセ作ったのかなぁと思って」
「はぁ?作ったけど?」
「手間がかかるって聞きました」
「そーね。でも作れないものじゃないし」
「栗だって別に好きじゃないし」
「だろうね」
「じゃあなんで」
そう聞くと、にこぉっと嬉しそうに笑った。
その顔は一ヶ月前に見た顔だった。
そして。
「似合うなぁと思って」
そして、ここ一ヶ月よく見る顔だった。
俺も顔を上げて彼の方を見た。
「嬉しいです」
うまく笑えているだろうか。
彼のように幸せそうに笑っているだろうか。
「大事にします」
ぎゅっと彼を抱きしめた。
ずっと、誰かの特別になりたかった。
だけどその他大勢で、選ばれることなく、それが嫌で、怖くて、誰にも近づかなかった。
特別なんて、どうやったらなるのか、どうやったらなれるのか分からなかったけど。
今が特別だって、確かに分かる。
「俺、カカシさん大好きです」
「単純だねぇ、アンタ」
「カカシさんほどじゃないです」
この人チョコレート貰ったぐらいで惚れたくせに。
そう思ったが、言ってやらない。
「カカシさん。俺のも腐らない術かけてください」
「はぁ?そんなものないよ」
「俺があげたチョコ流しの下に隠してるくせに」
俺があげた、チョコレートが二つとも。
そう言うとバツが悪そうにした。
それが可笑しくて笑うと力いっぱい抱きしめられた。
「いたたたたっ」
「アレはいーの。アンタのは欲しかったら何時でも作ってあげるよ」
「俺のだっていつだって買ったあげますよ!」
全く手をつけず、大事に隠されているチョコレート。きっと食べることなく、飾られていくのだろう。
アンタがほしいなら、いつだって、いくらだってあげるのに。
カカシさんはひどく驚いた顔をして、俺の肩に頭を置いた。
「くれるつもりなんてなかったクセに・・・」
「え?何ですか?」
小さくて聞き取れなかった。もう一回言って欲しかったのに、彼はグリグリと頭を押し付けるだけだった。
「じゃあ来年もね」
そんな当たり前のこと言って、馬鹿だなぁと思った。
「来年は俺、作りますよ!すっごいの!」
彼に負けないような凄いのを作って知らしめてやりたい。
俺だって彼が好きなことを。特別だってことを。
周りにも。
彼自身にも。
「ふぅん」
「その前に誕生日ですかね?ケーキ作りましょうか!」
「イルカ先生」
肩口から見上げるように俺を見た。色の違う目がこちらを見ている。
甘くてドロリとした目で。
「キスしたい」
それは彼が初めて口にした色の含んだセリフだった。
キスは特別な人に。
愛をこめて相手に触れる特別なコト。
そんなこと当たり前のように浮かぶのだから。
この人は特別なのだと思う。
「俺はずっと思ってましたよ!」
そう言って笑うと、またにこぉっと嬉しそうに笑ってくれた。
そして目を閉じた顔がゆっくり近づいてきた。
<終>
拍手ボタンを4/3に撤去いたしました。
Sponsored link
This advertisement is displayed when there is no update for a certain period of time.
It will return to non-display when content update is done.
Also, it will always be hidden when becoming a premium user.