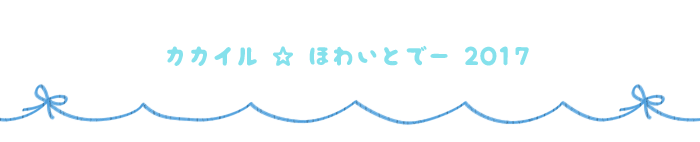天空「キャラメル ~一緒にいると安心できる~」
バレンタインの翌日は、散々だった。
カカシとのことが一部始終、里に知れ渡っていたからだ。
わざわざ火影岩という里で一番目立つ場所をあの男が選んだ意図に、あの時気付かなかったのが悔しい。
皆も動揺したのだろう。『あのイルカが、はたけカカシと付き合った』と、あの、の位置を間違えたままの噂は瞬く間に里を駆け巡り、翌朝には同僚たちから祝いの言葉とともに肩を叩かれまくり、夕方立ち寄った商店街では商店のおばちゃん達に「これからは二人分になるんだから」と買った量の倍ほどのおまけを押しつけられた。
同性同士の関係は忍の間では珍しくないものの、まだまだ一般的ではない。
それが。
写輪眼のカカシの名があるだけで、こんなにも祝福されるものになるらしい。
相手が高名だから面と向かって非難し辛いだけなのだろうと捻くれてみても、イルカの周囲の、まるで箱入り娘を玉の輿に担ぎ出したかのような喜び様は本物で、……それもなんだか悔しい。
夕食時、当たり前のようにイルカの家に帰宅してきたカカシにぎりぎりと歯噛みしながら報告したら、「それアナタの人徳デショ」と軽く笑って流されたのも悔しい。
確かにお付き合いは、しているけれど。
バレンタインのあの日、火影岩からまた瞬身でカカシの家に連れ込まれて、カカシのいろんなものを流し込まれたけれど。
カカシは里に戻ってきたら、真っ先にイルカの元に顔を出すようになったけれど。
里に居る間は、イルカの家で寝食を共にしているけれど。
でも。
別に俺はあの人に惚れてるってわけじゃないのだ、と、夕暮れの受付に座りながら、イルカはふんと鼻を鳴らす。
苦いチョコの殻をパキリと割ると、内部からどろりとリキュールの効いた、でも歯が浮くような甘さのジュレが流れ出して来たような。
はたけカカシという男は、そういう男だった。
好きだ好きだとシャワーのように浴びせかけられながら過ごす時間は濃密で、あまりの甘さに胃もたれがしそうだ。
あの男は絶対、釣った魚にえさを与え過ぎて肥満死させるタイプだと思う。
今でも時折辛辣なことを言われることはあるけれど、それは全て舌鋒鋭いだけの正論で。
しかも額当ても口布も何もかも脱ぎ捨てて隠すことをやめた男の表情は、イルカの為を思っての言動なのだと、その本心を容易くこちらに透けさせてしまう。
――どんだけ俺のこと好きなんだ、あの人は。まったく。
だだ漏れ過ぎて恥ずかしい。
だから、そう。惚れてなどいない。
ただ、騙し討たれて丸めこまれて、攫われて口説かれて絆されただけで。
俺は別にはたけカカシが好きなわけじゃない、とイルカはまた鼻を鳴らす。
「どうしたイルカ、風邪か?」
隣の席の同僚が、箱からティッシュを一枚引き出してこちらに差し出した。
遠慮なく受け取り力いっぱい鼻をかんで、乱雑に丸めたそれをゴミ箱に、ていっ、とシュートする。
「……っしゃあ!」
ガッツポーズを決めたイルカに苦笑を浮かべ、「子供か」と肩を竦めた同僚が正面に向き直る。
と、同時に「おい誰か」と声高らかに呼ばわりながら、綱手が受付所に入ってきた。
「おおイルカ、丁度いい」
なにがだ。
嫌な予感に思わず渋面で振り返ったイルカを見て、綱手は肩を揺らして笑う。
「良い顔をするようになったじゃないか、イルカ。幸せそうでなによりだ」
「……何か御用ですか?」
綱手のからかいを無視して、イルカは問い返す。
「これをな、カカシに持って行ってやってくれ。今ならまだ上忍待機所に居るはずだから」
ひょいと渡されたのは水薬の入った瓶だ。
「痛み止めさ。アイツは時々、写輪眼が酷く痛むようでね。だが処方してやっても、なかなか素直に飲まないんだ。――だから、丁度良かった」
恋人であるお前から良く言い聞かせてやっておくれ、と言い残し、綱手はまた颯爽と火影室へ引き返して行く。
反論する隙も与えぬ素早さは、さすが伝説の三忍といったところだろうか。
「それ届けたら直帰でいいから、行ってこいよ」
ぽん、と同僚に肩を叩かれて、イルカは渋々立ちあがる。
透明の液体が、イルカの手のうちでちゃぷりと揺れた。
――薬を飲みたがらないって、……アカデミー生でもあるまいに!
あンの我儘上忍め、とぶうっと唇をとがらせながら、イルカは本部棟の階段を上がる。
束ねた髪が、ちょうどイルカの頭上で響き始めた定時を告げる鐘に合わせて、わっさわっさと揺れている。
待機所から帰宅しようと出てきた顔見知りの上忍達が、ぐいぐいと階段の真ん中を進むイルカの横を、くすくす笑いながら通り過ぎてゆく。
「なんか、……なあ」
「ああ、懐かしいな」
などと言い合いながらイルカに向かってひらりと手を挙げたのは、アカデミーの上級生であった二人組だ。
ひとりは、イルカの入学式の時、入場行進の手を引いてくれた世話係のお兄ちゃんだった。
悪戯っ子で、しかも泣き虫であったイルカはその日、随分と彼の手を煩わせて、……結局卒業するまで『チビスケ』と呼ばれ続けたのは苦い思い出だ。
ぺこり、と下げたイルカの頭に、かつての世話係がぽんとその手を乗せて行き過ぎてゆく。
「お前はそっちの方が、らしいよ。チビスケ」
懐かしい愛称に目を丸くし、掛けられた言葉に首を傾げたイルカを見て、二人はまた笑い声を上げる。
「自覚ないのか、――重症だな」
「まあ、あれだ。幸せそうでなによりだってことだ」
笑いながら去っていく厳つい後姿を、イルカは呆然と見送る。
――なんだよ、皆して。幸せそう幸せそうって。
別にイルカの生活は、大して変わっていない。
いつも通り、仕事して、飯食って、寝ているだけだ。
カカシが居るか居ないかなんて、作る味噌汁の量が増えるか減るかくらいの、ほんの些細な違いだっていうのに。
良い顔をする、幸せそうだ、そっちの方がお前らしい。
カカシと付き合い始めて、ちょうど一ヶ月。
親しい皆から投げられる言葉は、イルカには意味がわからないものばかりだ。
あのクソ甘い上忍が、なにかイルカに良からぬ術でもかけているというのだろうか。
むむうと唸りながら、上忍待機所の前に到着する。
勢い良くドアに手をかけて、そこでイルカは、ぴたりと止まってしまった。
「――ねぇ、カカシ。あんな中忍なんて止めて、私にしない?」
聞こえた声に、とっさに気配を消して扉の陰に潜む。
ふわふわと花の香りでもしそうな甘い囁きは、同時に腰を直撃するほど蠱惑的だった。
迷わずカカシに照準を定めた全力の媚態に、――男なら、くらっとこない方が嘘だ。
扉越しに漏れ聞いたイルカの脳ですら、なにやら打撃を受けてツキンツキンと痛んでいる。
「あの男、人の良さそうな見た目に反して、随分面倒な性格だったんでしょう? わざわざ手間のかかる相手と付き合うなんて、貴方には似合わないわよ。ましてや、あんなむさ苦しい中忍」
くすくすと忍び笑う音すら艶を含んで媚びている。
「……貴方が望むなら、私、なんでもしてあげる」
きっとそれなりに容姿にも自信があるのだろうと窺い知れる言い方で、女は見事にシナを作った。
絶世の美女に傅かれて、そんな台詞を囁かれるだなんて。
――……あの野郎、リアルでイチャパラ世界に生きてやがる……っ!
じわり、とイルカの鼻先が熱を持って疼きだす。
イルカはカカシに喧嘩を売った覚えはあるが、特別何かをしてやった記憶なんてない。
ただ家に来たら飯を出して、一緒に食って喋るだけだ。
閨でだって、準備も後片付けも身体を清めるのも未だにカカシに任せっぱなしだし、誘われても気が向かなければ頑として首を縦に振らない。
依怙地で我儘で、可愛げなど欠片もない只の男と。
従順に己に従い、意のままになる麗しき乙女。
カカシがどちらを選ぶかなんて、そんなこと。
どちらと居たほうがあの男が幸せになれるかなんて、そんなの、もう。
「離れて」
低い低い声が、イルカの思考を遮断する。
「それ以上近寄らないで、アンタのその変な匂い、オレに移っちゃうデショ」
心底不愉快そうに、カカシが唸る。
「……何よ。あの中忍、そんなに嫉妬深いの?」
嘲るような言いざまに、イルカの頬がかっと染まる。
だがイルカの脳が反論するより早く、
「――違ーうヨ。アンタ馬鹿じゃないの」
それを切って捨てたのはカカシだった。
「オレが嫌なの。あの人以外の匂いが自分の身体からするなんて、耐えられない。アンタが何企んでるのか知らないけどさ、――オレはもう、あの人以外要らないの」
だから無駄だよ、と続ける。
「骨抜きでも首ったけでも好きなように言えばいいケド、オレはずっと前から、――とっくの昔に、あの人無しじゃ生きていけなくなってるの。死ぬまであの人だけでいい。それ以外欲しいと思えない。あの人が手に入らないなら、オレはそのまま餓死したい」
「……アタマおかしいんじゃないの!?」
ヒステリックに裏返った女の声にも、カカシは全く動じる様子が無い。
「そ、とっくの昔にイカれてんの。だからさ、そう報告すればいーよ、アンタの雇い主に」
「……っ」
女が息を飲む気配に、はっとイルカは我に返る。
「どーせ、上忍の血統が途絶えるのはどうのこうの、ってやつデショ? オレの写輪眼は血継限界じゃないし、種馬扱いは御免被りたいんだケド」
カカシはのんびりと、いつも通りの口調で淡々と話し続けている。
「あーでも、オレをあの人から引き剥がそうとしたり、物理的にあの人に何かしたら――迷わず殺すよ。オレが持ってるのはそういう種類の狂気だって、それだけ伝えておいて」
「……なんで、そこまで?」
問い返した女の声は、漂白された紙のように色が抜け落ちてまっしろだ。かさかさとしゃがれた音色は、とても先ほどと同一人物とは思えない。
くく、とカカシが笑う。
「失い過ぎたんだ。欠けた部分が多すぎて、もうどこが欠けてるのかすらわからない」
主語のない言葉は、一体カカシとイルカのどちらを指しているのだろう。
ぐう、と耳を擦った唸り声は、女のものだろうか、それともイルカの喉が立てた音だろうか。
「望むなら何でもしてアゲル? ――甘ーいネ」
呆れたようなため息を挟んで、カカシが続ける。
「オレは、あの人が望まないことまで、……ホントは何もかも、あの手から取り上げてやりたくて堪らないのに」
ず、と低く落ちた声に、イルカの心臓がどくりと揺れた。
「オレは、オレの全てをあの人で埋めたいの。あの人から向けられるモノなら、罵倒でも憎悪でも何でも良いんだよ。重くて面倒臭いなんて、むしろ望むところじゃない。世話をして手をかけてトロットロに甘やかして、いっそ、あの人がオレが居ないと何にも出来ないヒトになればいい」
ま、それを許してくれるような人じゃないんだケド、と何故かカカシは嬉しそうに笑う。
「あの人だけが、オレの飢餓を満たしてくれる。暴きたいのも、捕えたいのも、傍に居たいのも、触れたいのも、全部あの人だけだ。替わりなんてない。他に何も要らない。――……オレが望むモノは、もう、あの人だけなんだよ」
奪うなら狂うよ、と言ったカカシの声は、ひどく幸せそうだった。
土埃を立てながら、イルカは道を全力疾走していた。
ちゃぽんちゃぽんと手の中の水薬がせわしない音を立てる。
結局上忍待機所に入れないまま、本部棟を飛び出してきてしまった。
だって。
――きちんと飲むように、俺から言い聞かせろって。
そう、綱手から託されたのはそういう依頼だったはずだ。
だから。
脳裏で言い訳を浮かべながら、イルカは必死で家路を辿る。
心臓が煩いほど騒いでいるのは、走っているせいだ。
耳がちぎれそうなほど痛いのは、風が冷たいせいだ。
頬が上気しているのは、目が潤んでいるのは、鼻奥がつんとするのは。
――別に、アンタのことが好きだからじゃない。
ばたばたと玄関を開けると、もどかしく脚絆を脱いでイルカは部屋に飛び込んだ。
ず、と鼻を啜りあげながら、台所の戸袋を漁る。
続いて冷蔵庫を開け、冷凍庫を引っ掻き回す。
――薬を、ちゃんと飲むようにって。
そう言い聞かせてやらないといけないから。
あの、傍若無人で偉そうで、でも釣った魚にだけは、ただひたすら甘い甘い上忍に。
取り出した片手鍋に、イルカはパックの牛乳をだばだばと注いだ。続いて砂糖壺からざくざくと砂糖を振り入れて、凍ったままのバターを乱雑に落とす。
量りなんてないから、全部適当だ。
ただ記憶にある通りの材料を、イルカは鍋に放り込む。
昔、薬を飲むのが嫌いだったイルカに、母が作ってくれたお菓子があった。
キャラメルだ。
『これがあれば、お薬だって平気でしょう?』
そう優しく微笑んだ母の面影が、何故だろう、以前より遥かに鮮明に目の前に浮かぶ。
思い出す度にじくじくと疼いた胸の痛みは、嘘みたいに遠く霞んでいるというのに。
木べらも無くて、仕方なくしゃもじを鍋にぶち込んだ。
今はさらさらとしているこれが、水分が飛ぶにつれねっとりと、茶色みを帯びて来るのだ。
『母さんがね、父さんに初めて作ったお菓子なのよ』
照れくさそうに笑う母の動きに合わせて、ゆっくりと鍋の液体をかき混ぜる。
ふつりふつりと表面が泡立ち始めるにつれ、ふわりと甘い湯気が立つ。
慌てて換気扇をつけた拍子に、出しっぱなしの牛乳がイルカの目に飛び込んだ。
――せんせ、また出しっぱなし。
ふっと耳に馴染んだ男の声が蘇る。
そう叱られるのが既に日課のようになっているのに気づいて、イルカはぶるりと身を震わせた。
ぶんぶんと頭を振って幻聴を追いやりながら、牛乳を手早く冷蔵庫に仕舞う。
ぱたんと扉の閉まる音が、自分しか居ない空間に、やけに大きく響いた。
――畜生。
じわりと視界が揺れる。
そもそも、人が一人増えているのに、イルカの日常に負担が無い方がおかしいのだ。
なのに、あのいけ好かない上忍ときたら。
居るのか居ないのか気づけないほどふんわりと、居れば空気のように当たり前にイルカに寄り添っている。
――アンタと居ると、どんどん我儘になる……っ
受付に座っていると、時として理不尽な目に遭うこともある。
治まりきらないその腹の内を、よりによって深夜にSランク任務から帰還したカカシに向けたのはつい、先日のことだ。
だけど、あの夜だってイルカは黙って寝ようとしたのだ。
なのに。
悶々とした気持ちを抱えたまま、ぷいと背を向け寝ころんだイルカの腕を、あの男が引くから。
「イルカせーんせ、何かあったの?」
「別に」
「そ。……おいで、イルカ」
「なんで」
「なーんでも。いいから来なさい」
ぐいと身体ごと引き寄せられて、胡座をかいたカカシの足の上に抱き込まれる。
子ども扱いに膨れるイルカの思考を先回りするかのように「オレがイルカを抱きしめたいの。我儘聞いてよ」なんて言われてしまえば、もう反論も出てこない。
だからイルカは黙って、丁度イルカの顎あたりに来たカカシの頭をひたすら三つ編みにした。
南国土産の人形みたいなドレッドになるまで編み続けてやった。
明け方までかかった。
Sランク任務から戻ったばかりの男は、服も着替えず、身体の汚れも落とさぬまま。
ちりちりになったカカシの頭を見て、イルカが腹を抱えて笑い出すまで、――居眠りもせず、じっとイルカを抱きしめていた。
まるでそうするのが当然でもあるかのように。
イルカを抱くときだって、自分とそう変わらない体格の、むさ苦しい男の強張った身体を、飽きもせず辛抱強く開いてくれる。
カカシの吐く正論に貫かれたイルカが、反論できない悔しさに唇を噛み、ぐうと唸りながら頬を膨らませても。
酔っぱらったイルカが畳を転がって移動しながら、だらしない姿勢でテレビのリモコンに手を伸ばしても。
――……アンタが、笑うから。
イルカがカカシに駄目なところを見せるたびに、我儘を言うたびに、不貞腐れて拗ねるたびに、時に、理不尽に八つ当たりをするたびに。
カカシが、いかにも嬉しそうに笑うから。
品行方正であれ、いいひとであれとイルカが自ら身に着けた鎧が、ぽろぽろと剥がれていってしまう。
カカシの歯で殻を割り砕かれたイルカと言う名のチョコレートからは、一体どんな中身が零れているんだろう。
それは。
――それはちゃんと、カカシ好みの味なんだろうか。
イルカの鼻を、焦げた匂いが擽った。
はっと顔を上げると、鍋から薄い煙が棚引いている。
慌てて火を止め鍋を覗きこむと、記憶より随分濃い色になった液体が、マグマのように大きな泡を吹いて煮え立っていた。
「やべ……っ」
イルカは慌ててそれを、広げた油紙の上に流す。
どろりと流れたキャラメルから、湯気がふわりと立ち上る。
その香ばしくとろけるような匂いがイルカの脳に呼び起こす面影が……いつの間にか、二人から三人に増えている。
――畜生……っ!
ぐ、とイルカは歯を食いしばった。
甘いだけの仕上がりが悔しくて、八つ当たりでもするように、カカシの買ってきた岩塩をミルでごりごり振りかけてやる。
ばん、と冷蔵庫にそれを突っ込んで、そのままイルカは、ずるずるとその場にへたり込んだ。
「……俺は、アンタなんか、好きじゃねぇんだからな」
カカシが居なくなったって、イルカはきっと狂わない。
仕事して、飯食って、寝るだけの日常を、きっと普通に繰り返す。
あの男に貰っているのと同じ熱量を、返せる自信なんてこれっぽっちもない。
だからきっと、イルカはカカシを好きじゃない。好きなんかじゃない。
だけど。
カカシが離れていく未来を、イルカはもう許容できない。
『キャラメルにはね、一緒に居ると安心できる、って意味があるのよ』
あの人には内緒ね、と少女のようにはにかんだ母の顔が、伏せた瞼の裏に鮮やかに蘇る。
だけど『母さんの作るキャラメルが世界で一番うまい』と顔を綻ばせていた父はきっと、それを知っていたに違いない。
失ってしまった幸せな日々。
もう二度と、世界に裏切られたようなあの絶望を味わいたくなかった。
なのに。
――それなのに。
カカシとの日々は喪失の痛手を柔らかく癒して、イルカに新たな風を運んでこようとしている。
――こんなに、怖いのに……っ
「……アンタのせいだからな、バカカシ……ッ!」
イルカは冷蔵庫に背を凭れさせたまま、膝の間に顔を突っ込んで、震えながら少し泣いた。
---------
カカシが帰ってきたのは、丁度固まったキャラメルを切り分けているときだった。
煮詰め過ぎて水分の飛んだそれはまるで岩のような固さで、包丁に体重を乗っけてもなかなか刃が通らない。
台所で四苦八苦しているイルカを見つけて、カカシは楽しそうに眉を上げた。
「ただいま、せんせ。なんだか甘ーいイイ匂いするね。何してるの?」
手甲も額当ても早々に外したカカシは、口布を引き下ろしながらすたすたとイルカに近づいて、イルカの首元でスンと鼻を鳴らす。
「……そんなとこ匂っても、甘くないでしょう」
匂いのもとは、イルカの手元にあるのだから。
「ん? ああ、イルカの項はいっつもいい匂いだから、つい」
ごめーんね、とちゅっと音を立ててイルカの頬に口付けたカカシが、続いて、しょっぱい、と目を丸くする。
「泣いた?」
「泣いてないっ!」
間髪入れず返った答えに、カカシがくつくつと笑う。
「ま、いいケド。でも、オレが居ないトコで泣かないでよ。勿体ないじゃない」
「は? どういう意味ですか?」
「だって、――アナタの涙、甘くてしょっぱくて、美味しいんだもの」
もっと頂戴、とカカシが目尻に吸い付いてくる。
「……っ! はな、離せ、変態!!」
ダイレクトに目玉ごと舐めとられそうな勢いに、食われる! と暴れるイルカの目の端で、キャラメルに振り掛けられた塩の欠片がきらりと光る。
腹いせのつもりだったが、もしかしたら――……カカシ好みにカスタマイズしてしまったかも知れない。
イルカにつられてまな板に目を落とした上忍は、わあ、と嬉しそうに歓声を上げた。
「すごい! イルカ先生が作ったの!?」
その意外な反応に、思わずイルカは首を傾げる。
「……キャラメル、好きだったんですか?」
「え、だってこれ、バレンタインのお返しデショ?」
手作りのものが貰えると思わなかった、と微笑まれて、慌ててイルカはカレンダーを確認する。
三月十四日。
「……あっ!」
すっかり失念していた。
しかし、「ふふ、嬉しい」と顔全体で笑っている人に、今さら違うんですと誰が言えよう。
「――あの、これ、……これも!」
イルカはベストのポケットから取り出した水薬を、ええい、とカカシの鼻先に突き付ける。
「……あー。……ああ、うん……なるほど?」
カカシは片眉を上げ、しばし考えた後、からかうようにちらりとイルカを流し見た。
「ま、いいデショ。違うって言わなかったから、合格にしといてアゲル」
これもホワイトデーね、と水薬を受け取って肩を竦める。
「じゃ、きちんとお薬飲んだら、ご褒美にイルカ先生のキャラメル食べてもいい?」
どうやら全てお見通しになってしまったようだが、イルカもそこはあえて見ないふりをした。
「ちゃんと俺の前で飲んで下さいよ。綱手様に報告するんですから」
などと言いながら、腰に手を当てて精一杯の虚勢を張る。
「わかりました。――世界一美味しいキャラメルの為なら、頑張りましょ」
「世界一ってアンタ、まだ食べてないのに適当言って……っ!」
眉を吊り上げ頬を膨らませるイルカに、カカシの表情がとろりと解ける。
甘く柔らかい笑みに、イルカの胸がとくりと跳ねる。
「あのねぇ、せんせ。――世界一愛しい人が作ったモノが、世界一美味しくないワケないデショ」
「! ……ん、んぅ……っ」
イルカの涙のせいでしょっぱくなったカカシの舌を唇で受け止めながら、イルカの頬がにへっとだらしなく緩んでいるのを、――イルカだけが、まだ知らない。
終
Q.
ぶっちゃけ、外に居るの気付いてましたよね?
A.
「当り前じゃない。だから聞かれて困るコトは言ってないデショ?」
「――……~~~~っ!?!?!?!?」
拍手ボタンを4/3に撤去いたしました。
カカシとのことが一部始終、里に知れ渡っていたからだ。
わざわざ火影岩という里で一番目立つ場所をあの男が選んだ意図に、あの時気付かなかったのが悔しい。
皆も動揺したのだろう。『あのイルカが、はたけカカシと付き合った』と、あの、の位置を間違えたままの噂は瞬く間に里を駆け巡り、翌朝には同僚たちから祝いの言葉とともに肩を叩かれまくり、夕方立ち寄った商店街では商店のおばちゃん達に「これからは二人分になるんだから」と買った量の倍ほどのおまけを押しつけられた。
同性同士の関係は忍の間では珍しくないものの、まだまだ一般的ではない。
それが。
写輪眼のカカシの名があるだけで、こんなにも祝福されるものになるらしい。
相手が高名だから面と向かって非難し辛いだけなのだろうと捻くれてみても、イルカの周囲の、まるで箱入り娘を玉の輿に担ぎ出したかのような喜び様は本物で、……それもなんだか悔しい。
夕食時、当たり前のようにイルカの家に帰宅してきたカカシにぎりぎりと歯噛みしながら報告したら、「それアナタの人徳デショ」と軽く笑って流されたのも悔しい。
確かにお付き合いは、しているけれど。
バレンタインのあの日、火影岩からまた瞬身でカカシの家に連れ込まれて、カカシのいろんなものを流し込まれたけれど。
カカシは里に戻ってきたら、真っ先にイルカの元に顔を出すようになったけれど。
里に居る間は、イルカの家で寝食を共にしているけれど。
でも。
別に俺はあの人に惚れてるってわけじゃないのだ、と、夕暮れの受付に座りながら、イルカはふんと鼻を鳴らす。
苦いチョコの殻をパキリと割ると、内部からどろりとリキュールの効いた、でも歯が浮くような甘さのジュレが流れ出して来たような。
はたけカカシという男は、そういう男だった。
好きだ好きだとシャワーのように浴びせかけられながら過ごす時間は濃密で、あまりの甘さに胃もたれがしそうだ。
あの男は絶対、釣った魚にえさを与え過ぎて肥満死させるタイプだと思う。
今でも時折辛辣なことを言われることはあるけれど、それは全て舌鋒鋭いだけの正論で。
しかも額当ても口布も何もかも脱ぎ捨てて隠すことをやめた男の表情は、イルカの為を思っての言動なのだと、その本心を容易くこちらに透けさせてしまう。
――どんだけ俺のこと好きなんだ、あの人は。まったく。
だだ漏れ過ぎて恥ずかしい。
だから、そう。惚れてなどいない。
ただ、騙し討たれて丸めこまれて、攫われて口説かれて絆されただけで。
俺は別にはたけカカシが好きなわけじゃない、とイルカはまた鼻を鳴らす。
「どうしたイルカ、風邪か?」
隣の席の同僚が、箱からティッシュを一枚引き出してこちらに差し出した。
遠慮なく受け取り力いっぱい鼻をかんで、乱雑に丸めたそれをゴミ箱に、ていっ、とシュートする。
「……っしゃあ!」
ガッツポーズを決めたイルカに苦笑を浮かべ、「子供か」と肩を竦めた同僚が正面に向き直る。
と、同時に「おい誰か」と声高らかに呼ばわりながら、綱手が受付所に入ってきた。
「おおイルカ、丁度いい」
なにがだ。
嫌な予感に思わず渋面で振り返ったイルカを見て、綱手は肩を揺らして笑う。
「良い顔をするようになったじゃないか、イルカ。幸せそうでなによりだ」
「……何か御用ですか?」
綱手のからかいを無視して、イルカは問い返す。
「これをな、カカシに持って行ってやってくれ。今ならまだ上忍待機所に居るはずだから」
ひょいと渡されたのは水薬の入った瓶だ。
「痛み止めさ。アイツは時々、写輪眼が酷く痛むようでね。だが処方してやっても、なかなか素直に飲まないんだ。――だから、丁度良かった」
恋人であるお前から良く言い聞かせてやっておくれ、と言い残し、綱手はまた颯爽と火影室へ引き返して行く。
反論する隙も与えぬ素早さは、さすが伝説の三忍といったところだろうか。
「それ届けたら直帰でいいから、行ってこいよ」
ぽん、と同僚に肩を叩かれて、イルカは渋々立ちあがる。
透明の液体が、イルカの手のうちでちゃぷりと揺れた。
――薬を飲みたがらないって、……アカデミー生でもあるまいに!
あンの我儘上忍め、とぶうっと唇をとがらせながら、イルカは本部棟の階段を上がる。
束ねた髪が、ちょうどイルカの頭上で響き始めた定時を告げる鐘に合わせて、わっさわっさと揺れている。
待機所から帰宅しようと出てきた顔見知りの上忍達が、ぐいぐいと階段の真ん中を進むイルカの横を、くすくす笑いながら通り過ぎてゆく。
「なんか、……なあ」
「ああ、懐かしいな」
などと言い合いながらイルカに向かってひらりと手を挙げたのは、アカデミーの上級生であった二人組だ。
ひとりは、イルカの入学式の時、入場行進の手を引いてくれた世話係のお兄ちゃんだった。
悪戯っ子で、しかも泣き虫であったイルカはその日、随分と彼の手を煩わせて、……結局卒業するまで『チビスケ』と呼ばれ続けたのは苦い思い出だ。
ぺこり、と下げたイルカの頭に、かつての世話係がぽんとその手を乗せて行き過ぎてゆく。
「お前はそっちの方が、らしいよ。チビスケ」
懐かしい愛称に目を丸くし、掛けられた言葉に首を傾げたイルカを見て、二人はまた笑い声を上げる。
「自覚ないのか、――重症だな」
「まあ、あれだ。幸せそうでなによりだってことだ」
笑いながら去っていく厳つい後姿を、イルカは呆然と見送る。
――なんだよ、皆して。幸せそう幸せそうって。
別にイルカの生活は、大して変わっていない。
いつも通り、仕事して、飯食って、寝ているだけだ。
カカシが居るか居ないかなんて、作る味噌汁の量が増えるか減るかくらいの、ほんの些細な違いだっていうのに。
良い顔をする、幸せそうだ、そっちの方がお前らしい。
カカシと付き合い始めて、ちょうど一ヶ月。
親しい皆から投げられる言葉は、イルカには意味がわからないものばかりだ。
あのクソ甘い上忍が、なにかイルカに良からぬ術でもかけているというのだろうか。
むむうと唸りながら、上忍待機所の前に到着する。
勢い良くドアに手をかけて、そこでイルカは、ぴたりと止まってしまった。
「――ねぇ、カカシ。あんな中忍なんて止めて、私にしない?」
聞こえた声に、とっさに気配を消して扉の陰に潜む。
ふわふわと花の香りでもしそうな甘い囁きは、同時に腰を直撃するほど蠱惑的だった。
迷わずカカシに照準を定めた全力の媚態に、――男なら、くらっとこない方が嘘だ。
扉越しに漏れ聞いたイルカの脳ですら、なにやら打撃を受けてツキンツキンと痛んでいる。
「あの男、人の良さそうな見た目に反して、随分面倒な性格だったんでしょう? わざわざ手間のかかる相手と付き合うなんて、貴方には似合わないわよ。ましてや、あんなむさ苦しい中忍」
くすくすと忍び笑う音すら艶を含んで媚びている。
「……貴方が望むなら、私、なんでもしてあげる」
きっとそれなりに容姿にも自信があるのだろうと窺い知れる言い方で、女は見事にシナを作った。
絶世の美女に傅かれて、そんな台詞を囁かれるだなんて。
――……あの野郎、リアルでイチャパラ世界に生きてやがる……っ!
じわり、とイルカの鼻先が熱を持って疼きだす。
イルカはカカシに喧嘩を売った覚えはあるが、特別何かをしてやった記憶なんてない。
ただ家に来たら飯を出して、一緒に食って喋るだけだ。
閨でだって、準備も後片付けも身体を清めるのも未だにカカシに任せっぱなしだし、誘われても気が向かなければ頑として首を縦に振らない。
依怙地で我儘で、可愛げなど欠片もない只の男と。
従順に己に従い、意のままになる麗しき乙女。
カカシがどちらを選ぶかなんて、そんなこと。
どちらと居たほうがあの男が幸せになれるかなんて、そんなの、もう。
「離れて」
低い低い声が、イルカの思考を遮断する。
「それ以上近寄らないで、アンタのその変な匂い、オレに移っちゃうデショ」
心底不愉快そうに、カカシが唸る。
「……何よ。あの中忍、そんなに嫉妬深いの?」
嘲るような言いざまに、イルカの頬がかっと染まる。
だがイルカの脳が反論するより早く、
「――違ーうヨ。アンタ馬鹿じゃないの」
それを切って捨てたのはカカシだった。
「オレが嫌なの。あの人以外の匂いが自分の身体からするなんて、耐えられない。アンタが何企んでるのか知らないけどさ、――オレはもう、あの人以外要らないの」
だから無駄だよ、と続ける。
「骨抜きでも首ったけでも好きなように言えばいいケド、オレはずっと前から、――とっくの昔に、あの人無しじゃ生きていけなくなってるの。死ぬまであの人だけでいい。それ以外欲しいと思えない。あの人が手に入らないなら、オレはそのまま餓死したい」
「……アタマおかしいんじゃないの!?」
ヒステリックに裏返った女の声にも、カカシは全く動じる様子が無い。
「そ、とっくの昔にイカれてんの。だからさ、そう報告すればいーよ、アンタの雇い主に」
「……っ」
女が息を飲む気配に、はっとイルカは我に返る。
「どーせ、上忍の血統が途絶えるのはどうのこうの、ってやつデショ? オレの写輪眼は血継限界じゃないし、種馬扱いは御免被りたいんだケド」
カカシはのんびりと、いつも通りの口調で淡々と話し続けている。
「あーでも、オレをあの人から引き剥がそうとしたり、物理的にあの人に何かしたら――迷わず殺すよ。オレが持ってるのはそういう種類の狂気だって、それだけ伝えておいて」
「……なんで、そこまで?」
問い返した女の声は、漂白された紙のように色が抜け落ちてまっしろだ。かさかさとしゃがれた音色は、とても先ほどと同一人物とは思えない。
くく、とカカシが笑う。
「失い過ぎたんだ。欠けた部分が多すぎて、もうどこが欠けてるのかすらわからない」
主語のない言葉は、一体カカシとイルカのどちらを指しているのだろう。
ぐう、と耳を擦った唸り声は、女のものだろうか、それともイルカの喉が立てた音だろうか。
「望むなら何でもしてアゲル? ――甘ーいネ」
呆れたようなため息を挟んで、カカシが続ける。
「オレは、あの人が望まないことまで、……ホントは何もかも、あの手から取り上げてやりたくて堪らないのに」
ず、と低く落ちた声に、イルカの心臓がどくりと揺れた。
「オレは、オレの全てをあの人で埋めたいの。あの人から向けられるモノなら、罵倒でも憎悪でも何でも良いんだよ。重くて面倒臭いなんて、むしろ望むところじゃない。世話をして手をかけてトロットロに甘やかして、いっそ、あの人がオレが居ないと何にも出来ないヒトになればいい」
ま、それを許してくれるような人じゃないんだケド、と何故かカカシは嬉しそうに笑う。
「あの人だけが、オレの飢餓を満たしてくれる。暴きたいのも、捕えたいのも、傍に居たいのも、触れたいのも、全部あの人だけだ。替わりなんてない。他に何も要らない。――……オレが望むモノは、もう、あの人だけなんだよ」
奪うなら狂うよ、と言ったカカシの声は、ひどく幸せそうだった。
土埃を立てながら、イルカは道を全力疾走していた。
ちゃぽんちゃぽんと手の中の水薬がせわしない音を立てる。
結局上忍待機所に入れないまま、本部棟を飛び出してきてしまった。
だって。
――きちんと飲むように、俺から言い聞かせろって。
そう、綱手から託されたのはそういう依頼だったはずだ。
だから。
脳裏で言い訳を浮かべながら、イルカは必死で家路を辿る。
心臓が煩いほど騒いでいるのは、走っているせいだ。
耳がちぎれそうなほど痛いのは、風が冷たいせいだ。
頬が上気しているのは、目が潤んでいるのは、鼻奥がつんとするのは。
――別に、アンタのことが好きだからじゃない。
ばたばたと玄関を開けると、もどかしく脚絆を脱いでイルカは部屋に飛び込んだ。
ず、と鼻を啜りあげながら、台所の戸袋を漁る。
続いて冷蔵庫を開け、冷凍庫を引っ掻き回す。
――薬を、ちゃんと飲むようにって。
そう言い聞かせてやらないといけないから。
あの、傍若無人で偉そうで、でも釣った魚にだけは、ただひたすら甘い甘い上忍に。
取り出した片手鍋に、イルカはパックの牛乳をだばだばと注いだ。続いて砂糖壺からざくざくと砂糖を振り入れて、凍ったままのバターを乱雑に落とす。
量りなんてないから、全部適当だ。
ただ記憶にある通りの材料を、イルカは鍋に放り込む。
昔、薬を飲むのが嫌いだったイルカに、母が作ってくれたお菓子があった。
キャラメルだ。
『これがあれば、お薬だって平気でしょう?』
そう優しく微笑んだ母の面影が、何故だろう、以前より遥かに鮮明に目の前に浮かぶ。
思い出す度にじくじくと疼いた胸の痛みは、嘘みたいに遠く霞んでいるというのに。
木べらも無くて、仕方なくしゃもじを鍋にぶち込んだ。
今はさらさらとしているこれが、水分が飛ぶにつれねっとりと、茶色みを帯びて来るのだ。
『母さんがね、父さんに初めて作ったお菓子なのよ』
照れくさそうに笑う母の動きに合わせて、ゆっくりと鍋の液体をかき混ぜる。
ふつりふつりと表面が泡立ち始めるにつれ、ふわりと甘い湯気が立つ。
慌てて換気扇をつけた拍子に、出しっぱなしの牛乳がイルカの目に飛び込んだ。
――せんせ、また出しっぱなし。
ふっと耳に馴染んだ男の声が蘇る。
そう叱られるのが既に日課のようになっているのに気づいて、イルカはぶるりと身を震わせた。
ぶんぶんと頭を振って幻聴を追いやりながら、牛乳を手早く冷蔵庫に仕舞う。
ぱたんと扉の閉まる音が、自分しか居ない空間に、やけに大きく響いた。
――畜生。
じわりと視界が揺れる。
そもそも、人が一人増えているのに、イルカの日常に負担が無い方がおかしいのだ。
なのに、あのいけ好かない上忍ときたら。
居るのか居ないのか気づけないほどふんわりと、居れば空気のように当たり前にイルカに寄り添っている。
――アンタと居ると、どんどん我儘になる……っ
受付に座っていると、時として理不尽な目に遭うこともある。
治まりきらないその腹の内を、よりによって深夜にSランク任務から帰還したカカシに向けたのはつい、先日のことだ。
だけど、あの夜だってイルカは黙って寝ようとしたのだ。
なのに。
悶々とした気持ちを抱えたまま、ぷいと背を向け寝ころんだイルカの腕を、あの男が引くから。
「イルカせーんせ、何かあったの?」
「別に」
「そ。……おいで、イルカ」
「なんで」
「なーんでも。いいから来なさい」
ぐいと身体ごと引き寄せられて、胡座をかいたカカシの足の上に抱き込まれる。
子ども扱いに膨れるイルカの思考を先回りするかのように「オレがイルカを抱きしめたいの。我儘聞いてよ」なんて言われてしまえば、もう反論も出てこない。
だからイルカは黙って、丁度イルカの顎あたりに来たカカシの頭をひたすら三つ編みにした。
南国土産の人形みたいなドレッドになるまで編み続けてやった。
明け方までかかった。
Sランク任務から戻ったばかりの男は、服も着替えず、身体の汚れも落とさぬまま。
ちりちりになったカカシの頭を見て、イルカが腹を抱えて笑い出すまで、――居眠りもせず、じっとイルカを抱きしめていた。
まるでそうするのが当然でもあるかのように。
イルカを抱くときだって、自分とそう変わらない体格の、むさ苦しい男の強張った身体を、飽きもせず辛抱強く開いてくれる。
カカシの吐く正論に貫かれたイルカが、反論できない悔しさに唇を噛み、ぐうと唸りながら頬を膨らませても。
酔っぱらったイルカが畳を転がって移動しながら、だらしない姿勢でテレビのリモコンに手を伸ばしても。
――……アンタが、笑うから。
イルカがカカシに駄目なところを見せるたびに、我儘を言うたびに、不貞腐れて拗ねるたびに、時に、理不尽に八つ当たりをするたびに。
カカシが、いかにも嬉しそうに笑うから。
品行方正であれ、いいひとであれとイルカが自ら身に着けた鎧が、ぽろぽろと剥がれていってしまう。
カカシの歯で殻を割り砕かれたイルカと言う名のチョコレートからは、一体どんな中身が零れているんだろう。
それは。
――それはちゃんと、カカシ好みの味なんだろうか。
イルカの鼻を、焦げた匂いが擽った。
はっと顔を上げると、鍋から薄い煙が棚引いている。
慌てて火を止め鍋を覗きこむと、記憶より随分濃い色になった液体が、マグマのように大きな泡を吹いて煮え立っていた。
「やべ……っ」
イルカは慌ててそれを、広げた油紙の上に流す。
どろりと流れたキャラメルから、湯気がふわりと立ち上る。
その香ばしくとろけるような匂いがイルカの脳に呼び起こす面影が……いつの間にか、二人から三人に増えている。
――畜生……っ!
ぐ、とイルカは歯を食いしばった。
甘いだけの仕上がりが悔しくて、八つ当たりでもするように、カカシの買ってきた岩塩をミルでごりごり振りかけてやる。
ばん、と冷蔵庫にそれを突っ込んで、そのままイルカは、ずるずるとその場にへたり込んだ。
「……俺は、アンタなんか、好きじゃねぇんだからな」
カカシが居なくなったって、イルカはきっと狂わない。
仕事して、飯食って、寝るだけの日常を、きっと普通に繰り返す。
あの男に貰っているのと同じ熱量を、返せる自信なんてこれっぽっちもない。
だからきっと、イルカはカカシを好きじゃない。好きなんかじゃない。
だけど。
カカシが離れていく未来を、イルカはもう許容できない。
『キャラメルにはね、一緒に居ると安心できる、って意味があるのよ』
あの人には内緒ね、と少女のようにはにかんだ母の顔が、伏せた瞼の裏に鮮やかに蘇る。
だけど『母さんの作るキャラメルが世界で一番うまい』と顔を綻ばせていた父はきっと、それを知っていたに違いない。
失ってしまった幸せな日々。
もう二度と、世界に裏切られたようなあの絶望を味わいたくなかった。
なのに。
――それなのに。
カカシとの日々は喪失の痛手を柔らかく癒して、イルカに新たな風を運んでこようとしている。
――こんなに、怖いのに……っ
「……アンタのせいだからな、バカカシ……ッ!」
イルカは冷蔵庫に背を凭れさせたまま、膝の間に顔を突っ込んで、震えながら少し泣いた。
---------
カカシが帰ってきたのは、丁度固まったキャラメルを切り分けているときだった。
煮詰め過ぎて水分の飛んだそれはまるで岩のような固さで、包丁に体重を乗っけてもなかなか刃が通らない。
台所で四苦八苦しているイルカを見つけて、カカシは楽しそうに眉を上げた。
「ただいま、せんせ。なんだか甘ーいイイ匂いするね。何してるの?」
手甲も額当ても早々に外したカカシは、口布を引き下ろしながらすたすたとイルカに近づいて、イルカの首元でスンと鼻を鳴らす。
「……そんなとこ匂っても、甘くないでしょう」
匂いのもとは、イルカの手元にあるのだから。
「ん? ああ、イルカの項はいっつもいい匂いだから、つい」
ごめーんね、とちゅっと音を立ててイルカの頬に口付けたカカシが、続いて、しょっぱい、と目を丸くする。
「泣いた?」
「泣いてないっ!」
間髪入れず返った答えに、カカシがくつくつと笑う。
「ま、いいケド。でも、オレが居ないトコで泣かないでよ。勿体ないじゃない」
「は? どういう意味ですか?」
「だって、――アナタの涙、甘くてしょっぱくて、美味しいんだもの」
もっと頂戴、とカカシが目尻に吸い付いてくる。
「……っ! はな、離せ、変態!!」
ダイレクトに目玉ごと舐めとられそうな勢いに、食われる! と暴れるイルカの目の端で、キャラメルに振り掛けられた塩の欠片がきらりと光る。
腹いせのつもりだったが、もしかしたら――……カカシ好みにカスタマイズしてしまったかも知れない。
イルカにつられてまな板に目を落とした上忍は、わあ、と嬉しそうに歓声を上げた。
「すごい! イルカ先生が作ったの!?」
その意外な反応に、思わずイルカは首を傾げる。
「……キャラメル、好きだったんですか?」
「え、だってこれ、バレンタインのお返しデショ?」
手作りのものが貰えると思わなかった、と微笑まれて、慌ててイルカはカレンダーを確認する。
三月十四日。
「……あっ!」
すっかり失念していた。
しかし、「ふふ、嬉しい」と顔全体で笑っている人に、今さら違うんですと誰が言えよう。
「――あの、これ、……これも!」
イルカはベストのポケットから取り出した水薬を、ええい、とカカシの鼻先に突き付ける。
「……あー。……ああ、うん……なるほど?」
カカシは片眉を上げ、しばし考えた後、からかうようにちらりとイルカを流し見た。
「ま、いいデショ。違うって言わなかったから、合格にしといてアゲル」
これもホワイトデーね、と水薬を受け取って肩を竦める。
「じゃ、きちんとお薬飲んだら、ご褒美にイルカ先生のキャラメル食べてもいい?」
どうやら全てお見通しになってしまったようだが、イルカもそこはあえて見ないふりをした。
「ちゃんと俺の前で飲んで下さいよ。綱手様に報告するんですから」
などと言いながら、腰に手を当てて精一杯の虚勢を張る。
「わかりました。――世界一美味しいキャラメルの為なら、頑張りましょ」
「世界一ってアンタ、まだ食べてないのに適当言って……っ!」
眉を吊り上げ頬を膨らませるイルカに、カカシの表情がとろりと解ける。
甘く柔らかい笑みに、イルカの胸がとくりと跳ねる。
「あのねぇ、せんせ。――世界一愛しい人が作ったモノが、世界一美味しくないワケないデショ」
「! ……ん、んぅ……っ」
イルカの涙のせいでしょっぱくなったカカシの舌を唇で受け止めながら、イルカの頬がにへっとだらしなく緩んでいるのを、――イルカだけが、まだ知らない。
終
Q.
ぶっちゃけ、外に居るの気付いてましたよね?
A.
「当り前じゃない。だから聞かれて困るコトは言ってないデショ?」
「――……~~~~っ!?!?!?!?」
拍手ボタンを4/3に撤去いたしました。
Sponsored link
This advertisement is displayed when there is no update for a certain period of time.
It will return to non-display when content update is done.
Also, it will always be hidden when becoming a premium user.