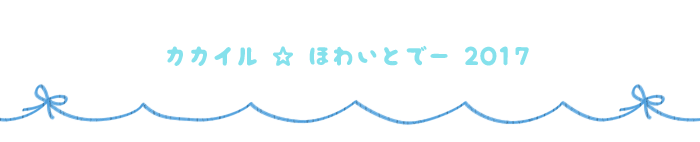pin「ティラミス ~私を元気づけて~」
実は俺たちって、友達だったのか?
カカシは呆然と隣にいるイルカを眺めていた。
場所は、三代目が保有している隠し別荘だ。
イルカにだけ教えてやる、と言った三代目が、イルカの頼みに渋々カカシも行って良しと認めてくれたのは、つい三日前の事だった。
「く…イルカよ、あの別荘はな、本当にいい所で、」
「知っていますよ、三代目も奥様としか行かない特別な別荘なんですよね」
「そこに…カカシとお前が…うっ…」
「ダメですか…?三代目…」
イルカの懇願の上目遣いに、三代目がかなうはずもない。
渋々といったていで、カカシと行くことに許可を出してくれ、そのままの足で喜び勇んでここに辿り着いた時には、もう日も暮れた夕方だった。
今日は、三月十三日。
つまり、いわゆる、ホワイトデー前日なのである。
そして、互いの休みも明日までだった。
ここの別荘についてから、イルカは恥ずかしそうにカカオの木を見せてくれた。
とても可愛らしい小さな木が3本植わっていただけの質素な見た目だったが、しかし、そのどれもが生き生きとしていて伸びやかな枝を見せつけていた。
大事に育てていたことがよく判る。
まるで生徒のように、木肌を撫でるイルカを見て、カカシも嬉しくて仕方がなかった。
確かにここは温泉地だけあり、気温も湿度も高い。
カカオの木が生息するのに充分な環境が整っていた。
カカシはイルカに言われて、牛も連れて来ていた。
背負って走るのはなかなかの骨だったが、地下室で飼うのは可哀想だ、というイルカの案を無碍には出来ない。
ここならば、草地も充分だし、広いし、管理人もいるしで、牛も生きやすいだろう。
確かに、カカシもバレンタインが終わる頃には忍犬のいる家に移動させるつもりでいたが、ここはそこよりも牛も居心地がよさそうだったのでカカシもホッとする。
イルカがこの別荘に来たがった一番の理由はそれだったのだ。
イルカが牛の背を撫でながら、嬉しそうに話しかける。
「ぎゅうさく!良かったな!」
「ん?ぎゅうさく?」
「この牛の名前です!」
「へえ…なんで、ぎゅうさく?」
「そりゃ、牛版サクラでぎゅうs」
「待って待って、それ、完全にダメなネーミングだから!」
イルカのイルカ節に何度もツッコミをいれつつ、それでもこの三日、本当に楽しく過ごしていた。
一緒に、ぎゅうさくの乳で、ヨーグルトを作ったり、チーズを作ったり。
そしてあのカカオ豆でチョコレートを作ったり…。
夜はゆったりと温泉に浸かりながら、子供たちの事で語らい、そしてふかふかの布団で寝る。
夢のように楽しい時間を過ごしていた。
そう、まるで、親友のように。
(まずい)
カカシが、イルカを横目で眺めながら、唇を噛みしめる。
カカシは、気づいていた。
前回のバレンタイン。
実はお互いに、「好き」だと伝えていない事に。
勿論カカシはそういうつもりだった。
一世一代の大告白のつもりで、異国でグランプリを取得したという乳牛の買い付けまでしたのだが、もしかしたら、イルカは、いわゆる友チョコという物のためにカカオの木を用意していたかもしれない。
・・・有り得る。
噛んだ唇がじんじんと痛い。
そう、有り得そうなのだ。
牛にぎゅうさくと名付けてしまう、このど天然のイルカならば。
カカシの目にはぎゅうさくとカカオの木。
そして牧歌を楽しむ眩しいイルカ。
これは違う。
いや、これはこれで楽しいが、恋人になって初めてのイベントがこれでは、何か違う。
・生徒を大事にするイルカ先生。
・ナルトを弟のように溺愛するイルカ先生。
・牛やカカオにさえも愛情を注ぐイルカ先生。
・友達を恋人のように大切にするイルカ先生←new!
嫌な妄想が頭をはびこり、こめかみが痛い。
何がnewだ。カカシはイルカの恋人なのだ。友を超えた…はずなのだ。
と、自信をもって言えないのが、カカシの。そして、イルカのイルカたる所以である。
カカシは、これではいかんと、このホワイトデーにかこつけて奮起するのである。
・・・
「好き好き好き好き好き好きっききききすすいきs」
カカシは口の中で必死に、イルカの前で言おうと練習を繰り返す。
壁に向かってブツブツいっていれば、背後ではイルカがニコニコしながら、ぎゅうさくチーズを冷蔵庫から取り出していた。
何やら料理を作るつもりらしい。
思えば、こんな僻地の別荘でよくこれだけの物を作れたな、と思うほどの料理がイルカから紡ぎ出されていた。
なんでもかんでも、材料から手作りしてしまうのは、どうやらイルカの性分のようだ。
(でも、枕が合わないと言ったら、昼間に打ったソバの殻でそば殻枕を作りだしたのには流石にビックリしたけど)
しかも、絶妙な高さが心地よくて、そのまま里に持って帰ろうと思う程だ。
正に、生活の知恵の生き字引。
「どうしたんですか?カカシ先生。元気ないですね?」
考えすぎていたのか、心配そうに顔を覗き込むイルカに、ハッとなってカカシも苦笑する。
「いや、イルカ先生はなんでも手作り出来て凄いなって思って」
「あー、そうですね。手作りは好きなんですよ」
「誰かの影響ですか?」
「ええ、親の影響ですね」
「へー!お父さんとお母さんも手作り派だったの」
その影響が、今こうしてカカシにも行使されているのだとすれば、なんだか自分もイルカの家族になったようで嬉しい、なんてニヤニヤしてしまう。
が、すぐに「いえ」と手を翳して否定される。
「いたずらを仕掛ける時、大体は家の中の材料が減っていてバレる事が多かったんですよ。うちの親は鋭いわ大人気ないわで、俺のいたずらも忍者の技を駆使して逃げたり壊したりしてきたもんだから俺も意地張っちゃって。材料の減りでバレるなら、外から調達して自分で作るしかなくて。近所の松の木とか手頃な材料になったんでいつも折ってその家のオヤジに怒られ」
「うん、わかったから黙って」
相手はイルカである。うっかりと忘れる所であった。
「そういうカカシ先生だって、手作り好きですよね?でないと、わざわざチョコを手作りなんて」
イルカの問いに、たしかに、とカカシも頷く。
「そうですね…俺も思いを伝えるのには、手作りが一番って刷り込みが…。ああ、俺も父さんの影響かも」
「サクモさんが!」
興味津々に目を輝かせるイルカに少し照れながら、頭の中では遠き日の父を思い出す。
懐かしい父の姿に思いを馳せて、ああ、自分も、あの頃の父の気持ちに寄り添えるようになったんだなと温かい気持ちになってくる。
「父親が母親にプロポーズするとき、ダイヤの鉱山を買い取って、一人で」
「判りました。うん。サクモさんすごいな!」
自分の白い牙の異名をもじって、ダイヤモンドを牙の形に掘って母に渡した所、母に、「まあ頑丈な入れ歯ね!有難う」と言われ、
更に惚れたという話をしたかったのだが、どうやら、させてもらえないようだ。
カカシはこのエピソードを父から聞くたびに、バカップルを通り越したダブルボケ夫婦と呼んでいたのだが、それがカカシの理想の家庭の形となって心に根付いていたとは、無意識とは本当に恐ろしい。
そうこう言っている間に、イルカが何やら作り出す。
どうやらお菓子のようだ。
シャカシャカと楽しそうな音がボールの中で踊る。
「先生、それは何?」
カカシがボールをのぞき込むのに、イルカがニヤリと笑う。
「ティラミスというお菓子を作ります」
「肉食恐竜が間違いを犯しちゃったって感じの」
「ああ、ティラノサウルスがミスを犯す、ティラがミス、ティラミスね。違います」
最近、思考を読まれているのか、イルカに言葉遊びを仕掛けても瞬殺されるカカシである。
これはこれで、仲が良いようなくすぐったい感じが嬉しい。
「ちょうど、ぎゅうさくのミルクで出来た生クリームとチーズがあったので」
「コーヒーもいれるの?」
「生地に染み込ませるんですよ。そうすると苦味が甘さを引き立てます」
「へえ・・・」
「今作っておけば夜には食べられますよ」
「そんな時間がかかるんだ」
「1時間くらいで固まりはするんですけどね。でも、こういうのは冷えてる方が美味しいものです」
「冷えてるほうが…」
「そうそう。待つのもまたお菓子作りの楽しさですよ」
「待つ…」
冷えるのを待つだなんて。
イルカの言葉に、ざわりと胸が騒いだ。
まるで、カカシが恋に飽きるのを待つと言われているかのように聞こえたからだ。
恋人ごっこも、冷えるのを待てば、すぐ終わる、と。
途端に胸に穴があいたような感覚に襲われる。
近づいたと思っていた距離も、本当は平行線だったと思い知る。
早く、言わなければ。
早くイルカに好きだと。
早くイルカと、本当の恋人になりたいと。
でなければ、このまま自然消滅で、イルカはカカシから去って行く。
まるで、冷蔵庫に入れて、冷めるのを待つかのように。
あのティラミスの苦味は、きっとカカシを雁字搦めにしてしまうだろう。
そして、ペロリと食べられ跡形もなく消えてしまう。
その前に。
言わなければ。
「…好きだよセンセ」
口の中から出て行こうとしない声に、「俺もですよー」と遠くの方で能天気な幻聴が聞こえた。
・・・
「好き好き好き好き好き好きっききききすすいきs」
カカシが露天風呂に浸かりながら、水の中でブツブツ呟くのに、イルカが覗き込んでくる。
「カカシ先生、溺れてます?疲れましたか?」
「いいえ、イメージトレーニングです」
「ははあ、流石上忍様。いついかなる時も修行という訳ですね」
「上忍とか関係なく、人間として残りの人生の幸せをかけた戦いに挑むのです」
「なるほど。我々にとっては重要な課題ですね」
「まさしく」
「頑張ってください。俺は先帰りますね」
「へえ」という言葉を残して、イルカが何に納得したのか判らないまま風呂から出ていくのを、カカシは眺めて。
また鼻下まで沈みながらイメージトレーニングを続ける。
実は、好きだと言うのは簡単だ。
しかし、その後の展開が読めない。
なんといっても、あのトリッキーイルカである。
「俺も好きですよ!親友です!」と答えられた時のダメージは計り知れない。
そこからの巻き返しに、どういう言葉や行動をとれば良いのか、が今のカカシのイメトレ内容であった。
1:親友を超えたいと言ってみる。→大親友です!と答えられる可能性が高い。
2:愛してると言ってみる。→友愛とは美しいですね、と答えられるに違いない。
3:襲い掛かる。→火影行き決定。
「うーむ手ごわい」と唸りながらも、口では好きという練習を怠らない。
お湯の中で、カカシの言葉はかき消されながらも水泡を作って浮かび上がる。
パチンと消える泡に、カカシは苦笑した。
しかし。
すぐに、思考をぶち破るような高い鳥の声が聞こえた。
見上げると、馴染みの鳥が上を飛ぶ。
キューイと何回か鳴いた鳥は、カカシの頭の上を一回旋回すると、ひらりと紙を落として飛び去っていった。
湯を避けるように離れた所でひらひら舞ってくる紙を、手を伸ばして受け取る。
カカシは、その内容を確認するや否や、
すぐさま服を羽織って、露天風呂から飛び出した。
嫌な予感はずっとしていた。
事の発端は先日の、紅が行った任務だ。
隊一個分の人数を引き連れて、紅は言葉の通じない異国へと向かった。
そして翌日。
帰ってきたのは、紅をいれてわずか5人だったのだ。
罠だという事は最初からこっちだって判っていた。
ある特殊な知識のあるものを一掃するかのように集めて任地へ行かせるなど、普通では考えられない。
あの時は、多言語を理解できるものが集められた。
その直後。
植物学に長けている者が、動物を使役できる者が、体術が得意な者が、と次々と隊を組んで任地へ飛ばされていく。
人間には得手不得手がある。
ある特定の分野に熟達していれば、必ず、対になる短所があるのだ。
そして、隊をなすほどに集まった彼らは、同じ方向性の知識しか持ちえない。
つまり、不測の事態に陥った時。
さらに彼らの得意分野が使えない場面に出くわした時。
隊はあっという間に崩れてしまうという事だ。
実に回りくどく、そして奇妙な罠だった。
最初にその依頼が来た時から、警戒はしていた。
隊にはバランスが大事だ。
そのバランスを、あえて崩すような内容の依頼。
カカシは【依頼人を調査する】という依頼を請け負っていた。
似た内容の依頼にも関わらず、依頼人は毎回違う。
その依頼人全員に、カカシの影分身が張り付いていた。
今の鳥は、カカシ本体からの命令だ。
今から、行くと。
ここに、カカシが来ると。
イルカの元へカカシが来ると。
そう。
『依頼人の一人であるイルカ』の元へ。
カカシは、急いで別荘内にいるイルカの元へ瞬身の術を切る。
・・・
「イルカ先生…」
イルカは台所にいた。
手にはワイングラスに綺麗に盛り付けられたお菓子がある。
「あ、カカシ先生、さっき作ったティラミス、うまく出来ましたよ!!見てください、この完璧な層のハーモニー!」
両手に掲げるように見せてニコニコ笑うイルカに、心が痛む。
「先生…」
「ほら、甘いの食べると元気になりますよ!風呂上りですよね、冷えててちょうどいいはずです」
そんなイルカの言葉もろくに聞かず、
差し出すイルカの手をすり抜けて、カカシがイルカを抱き寄せる。
イルカは突然のカカシの行動に驚いて、両手にティラミスを持ったまま固まってしまった。
「か、カカシ先生!?」
「イルカ先生…」
慌てるイルカの体を両手で強く拘束して。
そして、すぅっと。
イルカの背に回した手で、首筋にクナイを突き付けた。
「カカシ先生」
二回目に呼びかけてくるイルカの声は酷く冷静だった。
「ねえ、誰が依頼主なの?」
イルカの体がわずかに身じろぐ。
「あの任務、イルカ先生が発案者?ねえ、どこからどこまでが貴方の策なの?俺の事も、嵌めようとしていたの?」
カカシの心がどんどん暗くなる。
自分の言葉に傷ついて。自分の考えが追い打ちをかける。
一番、裏切ってほしくない人が敵だったなんて、誰だって考えたくない。
「先生…好きだよ」
言いながら、カカシはイルカのうなじに刃をあてた。
「帰ってこなかった残りの仲間は、どこにいる」
イルカはくすりと笑う。
「ああ、このカカシ先生は、本物なんですね。じゃあ言う相手を間違えてたんだ俺」
イルカの声はいつも通りの明るさで。
そして息を上げながら、イルカの目の前に立つカカシの影分身にイルカは微笑んだ。
「ね、カカシ先生。さっき作ったティラミスうまく出来ましたよ。風呂上りにどうですか?」
途端に、腹の底から苛立ちの塊がせりあがって来て、カカシは勢いに任せて自分の影分身にクナイを投げつける。
クナイは影分身をかき消しながら、床へ刺さった。
「先生」
「何が聞きたいですか?」
静かな声が耳そばで囁かれる。
「全部」
それに間髪入れずに答える。
全部だ。勿論全部に決まってる。
「目的、依頼主、仲間の行方、あなたの真意。全部に決まってる」
「そうですね…」
イルカはため息のように息を吐くと、するりとカカシの腕の中から身をかがめて出ていく。
「先生」
「じゃ、そこにどうぞ。話しましょう」
台所の椅子にカカシを勧めるイルカは。
まるで受付で依頼を言い渡すかのようだった。
****
台所の机に、二人で向かい合わせに座る。
「まず、俺の依頼主は、火影様です」
「…」
「カカシ先生の依頼主は?」
「…ホムラ様です」
互いが頷く。
「…そうか…まさか、カカシ先生がホムラ派だったとは…」
「それはこちらのセリフです。まさか先生が火影派だったなんてね」
「カカシ先生は、写輪眼関連ですか?」
「まあ、そうですね。イルカ先生の方が意外だよ。てっきり働きすぎとかで何かしら健康診断引っ掛かると思ってたのに」
「残念ながら、全てがA判定でした」
「むううう、悔しい。けど、それはそれで嬉しい」
時間は、バレンタインの前の週に戻る。
火影である三代目と、ご意見番のホムラは里の現状を憂いていた。
ちょうど居合わせたカカシは、二人の愚痴を聞かされ、なかなか帰れない状況に些かぐったりとしていた。
「まったく、バレンタイン?浮かれおってからに、最近の若者はけしからん」
ホムラのセリフに、三代目も深く頷く。
「全くじゃ。・・・と、そういえばカカシも。お主、異国まで牛を買いに行ったそうじゃないか」
「はあ…」
「なんじゃとう!?まさか、バレンタインに関連するんじゃなかろうな」
「いや、しますね」
「っかーーー!なんということじゃ。緊張感が足りん!里にいようともお主らは忍じゃろうが!」
「はあ…しかし、たまにはお祭り騒ぎをするのもいいじゃないですか」
こんなイベントがなければ、告白することもままならない位に忙しいのだ。
1年に一度くらい、本気で遊んだっていい、とはカカシの意見である。
「イルカの奴も何やら企んでいるようだしのう。あやつは昔からいたずら癖が抜けんで困る」
「嘆かわしい。たるんどるのお…よし、ここはひとつ、里の忍たちに儂らが気合いをいれてやろうじゃないか」
ホムラの思いつきに、三代目が食いつく。
「ほほお?どうするんじゃ?」
「里の忍ども同士で競わせよう」
「おお、面白そうじゃな」
「忍をまず、二チームに分ける。で、相手のチームの忍を多く倒した方が勝ち」
「いいのういいのう!じゃあ、どうチームを分けようかの!」
「おあつらえ向きに、健康診断が明日あろう。それの結果で分かれるというのはどうじゃろう」
「面白い!早速通達じゃ!」
つまりは、バレンタインという恋のイベントに全く興味も関係もない老人たちが拗ねた結果、こうしたよく判らないイベントが同時開催されることになったのだ。
イルカは、健康診断でA判定組火影チーム。
カカシは、健康診断で要再検査組ホムラチーム。
期限はホワイトデーまで。
チーム分けされた忍たちは、お互いがどちらのチームかすら判っていない。
そんな状態で相手の戦力を削いでいく。そして最終日にメンバーが多く残っていたチームが勝利。
そんなゲームだった。
勿論、本当に決闘などをすれば、強い上忍がいるチームが勝ってしまう。
そのため、《ケイドロ》のルールが採用された。
つまり、罠に引っ掛かった忍たちは、敵チームのとある場所に隔離されるのだ。
隔離された忍たちは、誰かが助けるか、ゲームが終わらない限り、そこから動くことはできない。
つまり、せっかくのバレンタインデーやホワイトデーを、隔離されて過ごす忍が多数現れるということだ。
それが、浮かれた若者たちへ喝をいれたい老人たちの思惑だったのだから、老獪としか言いようがない。
「紅や一緒に帰ってきたあの5人の仲間は、火影チームだったんだね」
「その通りです」
「ねえ、仲間の居場所はどこ?どこに隔離しているの?」
「あと少しでゲームセットです。それが終わったらお教えしますよ」
「今の所、うちのチームは負けてる?」
「さあ?俺には判りかねます」
「うそだ。忍を管理している受付忍がどっちのチームでも参謀になっているって聞いたよ。火影チームはイルカ先生でしょ」
「ふふふ、そうですねえ?」
「ねえ、先生。いい子だから」
カカシが出来るだけ優しく、イルカの頬を撫ぜる。
それにイルカは少しだけ気持ちよさそうに目を細めるも、しかしニコリと笑うだけだった。
いつもは心の声まで駄々漏れのイルカが、こうして口を閉ざしているということは、彼は今、忍モードだ。
この別荘にきた瞬間から、それは始まっていたに違いない。
最初からイルカには、カカシは敵だと知っていたという事なのだ。本当に侮れない。
「ほら、カカシ先生。とりあえずティラミスをどうですか?」
「先生、俺たちバレンタインデーで付き合う事になったよ?他の忍たちにも幸せを分けてあげようとは思わない?」
「おやおやー?さっきまでのカカシ先生は、俺と本当に付き合ってるのか疑ってましたけど?」
「だってあの影分身は、バレンタインデー直後に作った奴だもの。その後の俺たちを知らないから仕方ないよ」
「あんな純情なカカシ先生もいたんだなって少し感動していました」
「バレンタイン前の俺はあんな感じだったんだよ可愛いでしょ?さ、他の恋する忍たちにもチャンスをあげようよ」
「そんな事いって。この勝負に勝ったチームに与えられる商品を知ってるからそう言ってるんでしょ?」
にやりと笑うイルカに、カカシも苦笑する。
「そりゃあ、ねえ…?」
「俺だって興味ありますもん。勝ちに行きますよ」
「うーん…じゃあ仕方ないなあ…」
「仕方ないですねえ…」
ピキンと二人の間に緊張が走る。
そして、間をおかずにカカシが、ガンと机を叩いた。
「ティラミス早食いで決闘はどうだ!」
「のった!」
そうして、13日の夜が更けていったのである。
・・・
かくして、14日の当日は里中が大変だった。
普段、バレンタインやホワイトデーを意識していない者まで頑張る事態となったためだ。
当日、里に残っていた、いわゆる逃げ切った勝ち組の忍たちは、こぞって告白劇を繰り広げ、
成功すればよいが、勿論玉砕した者も大勢現れた。
また、囚われた忍たちも、囚われた者同士で致し方なくくっついたりと、悲劇と喜劇のダブルパンチで、阿鼻叫喚の様相があらゆる所で繰り広げられたのだ。
更に。
この一か月、お互いを疑い警戒しながらの生活をしていたために、付き合っていたカップルの破局率も大幅に上がってしまうというオマケまでついてきた。
当然、任務達成率もさがった。
そのため、諸悪の根源である、三代目とホムラはイルカ達受付忍に説教される羽目となったのである。
そこで、勝者であるイルカチームの要請で、火影はこう宣言した。
「バレンタインデーとホワイトデーのやり直しを一週間後に設ける」と。
勝者チームへの商品は、火影に一つ、願いをかなえてもらう権利だった。
参加していた忍のほぼ全員が、中長期の休みを切望していた。
が、今回の火影たちの陰謀により、里の恋愛事情はめちゃくちゃになってしまった。
だから、この一か月をなかったことにして再度仕切り直そう、というのがイルカ達の要求となったのである。
「ほら、いつまで拗ねてるんですか、カカシ先生」
部屋であぐらをかいて、いつもの本を読むカカシに、イルカが声をかける。
驚いた。
拗ねてる様子なんて、見せていないと思っていたのに。
「拗ねてなんか」
一応、そう伝えてみるが、イルカにはバレバレのようだ。
「いいえ、拗ねてますよ。そんな悔しかったですか?早食いに負けたの」
「だって、あんなに甘いと思わなかったからね…」
嘘だ。
食べた事のない未知の食べ物ティラミス。
コーヒーの苦味は、カカシの苦手な甘みを消してくれていると思った。
あるいは、甘かったとしても、修行の一環だと思えば耐える事が出来るものだと思った。
ところが、一口食べた瞬間に、その思いが打ち砕かれた。
お菓子が甘かったんじゃない。カカシの考えが甘かった。
カカシのために作られたティラミスは、
カカシ好みに甘すぎず、とろけて。
程よい苦みがアクセントになって。
そして、なにより冷たくて美味しかった。
早食いなどしたら、勿体ないと思うほどに。
そもそも、イルカの作った食べ物で早食いなど、カカシには最初から勝機などなかったのである。
「全く。こんなのいくらでも作ってあげるのに何を考えてるんだか。はい、カカシ先生。ティラミスどうですか?」
いつものように心の声まで駄々漏れにさせながらもイルカの手には、あの時のようにティラミスが乗っている。
別荘の時のようにおしゃれなグラスには入っていなかったが、しかし、間違いなくイルカの作ったイルカのお菓子。
肩をすくめてイルカから受け取った器は、やはり程よく冷たかった。
少しばかりささくれて熱をもった心に、ちょうどいい。
別に早食いに負けた事などどうでもよかった。
ただ、あの時、自分の影分身が考えていた事がどうしても心をひっかいていく。
ティラミスを作るイルカを見て、イルカの気持ちが冷めると勘違いした自分の影の気持ちはよく判る。
あの時、焦った気持ちは、確かにカカシの気持ちだった。
イルカは誰にでも優しい。
それはイベントのやり直しを要求した所からも見て取れる。
もう一度、恋する忍にチャンスをと。せっかくの特権を使って仲間のために気を配る。
それは、いささか行き過ぎた愛だと、カカシは思う。
友達どころか、会話をしたことさえもない仲間のためにイルカは優しさを振りまくのだ。
まるで恋人を甘やかすように。
でも、それでも。
目線を落とすと、そこにはイルカのティラミス。
手の中のそれは、カカシの体温を少し奪いながら、するすると体に入ってくる。
こうして、カカシの体調や気持ちを一番に考えて、タイミングよくティラミスを出してくれるのはカカシだけの特権なのだ。
「ね、先生、好きだよ?」
呟くようにカカシが言うのに、イルカもニコリと笑う。
「俺も好きですよ!大親友です!」
「う・・・」
今このタイミングでイルカに言えば、こう返されるとは思っていたが、実際言われると本当にダメージが凄い。
冗談と判ってはいてもこれだけの衝撃なのだから、あの時、同じ事を言われていたら立ち直れなかったに違いない。
イルカが笑いながら、落ち込むカカシの頭を撫ぜる。
「皆もうまく行くといいですね、やり直しバレンタイン」
皆も。
そのたった一言だけで救われる。
自分たちはうまく行っているのだと、隠れた言葉がカカシを安堵させる。
最近、イルカはこうした小さな言葉遊びをしかけてくる。
それは、きっとカカシに影響された癖で。
カカシは、弄ばれてるなあと思いながらも「そうだね」と苦笑する。
そして、残りのティラミスを口にいれるのだ。
ティラミス。
怒りや悲しみで熱くなった体を冷やして。
苦さで叱り、甘さで慰めて。
そうして、私を元気づけて。
一週間後、里では、泣きながらティラミスをバケツ食いする里民が急増したのは、また別の話である。
<終>
拍手ボタンを4/3に撤去いたしました。
カカシは呆然と隣にいるイルカを眺めていた。
場所は、三代目が保有している隠し別荘だ。
イルカにだけ教えてやる、と言った三代目が、イルカの頼みに渋々カカシも行って良しと認めてくれたのは、つい三日前の事だった。
「く…イルカよ、あの別荘はな、本当にいい所で、」
「知っていますよ、三代目も奥様としか行かない特別な別荘なんですよね」
「そこに…カカシとお前が…うっ…」
「ダメですか…?三代目…」
イルカの懇願の上目遣いに、三代目がかなうはずもない。
渋々といったていで、カカシと行くことに許可を出してくれ、そのままの足で喜び勇んでここに辿り着いた時には、もう日も暮れた夕方だった。
今日は、三月十三日。
つまり、いわゆる、ホワイトデー前日なのである。
そして、互いの休みも明日までだった。
ここの別荘についてから、イルカは恥ずかしそうにカカオの木を見せてくれた。
とても可愛らしい小さな木が3本植わっていただけの質素な見た目だったが、しかし、そのどれもが生き生きとしていて伸びやかな枝を見せつけていた。
大事に育てていたことがよく判る。
まるで生徒のように、木肌を撫でるイルカを見て、カカシも嬉しくて仕方がなかった。
確かにここは温泉地だけあり、気温も湿度も高い。
カカオの木が生息するのに充分な環境が整っていた。
カカシはイルカに言われて、牛も連れて来ていた。
背負って走るのはなかなかの骨だったが、地下室で飼うのは可哀想だ、というイルカの案を無碍には出来ない。
ここならば、草地も充分だし、広いし、管理人もいるしで、牛も生きやすいだろう。
確かに、カカシもバレンタインが終わる頃には忍犬のいる家に移動させるつもりでいたが、ここはそこよりも牛も居心地がよさそうだったのでカカシもホッとする。
イルカがこの別荘に来たがった一番の理由はそれだったのだ。
イルカが牛の背を撫でながら、嬉しそうに話しかける。
「ぎゅうさく!良かったな!」
「ん?ぎゅうさく?」
「この牛の名前です!」
「へえ…なんで、ぎゅうさく?」
「そりゃ、牛版サクラでぎゅうs」
「待って待って、それ、完全にダメなネーミングだから!」
イルカのイルカ節に何度もツッコミをいれつつ、それでもこの三日、本当に楽しく過ごしていた。
一緒に、ぎゅうさくの乳で、ヨーグルトを作ったり、チーズを作ったり。
そしてあのカカオ豆でチョコレートを作ったり…。
夜はゆったりと温泉に浸かりながら、子供たちの事で語らい、そしてふかふかの布団で寝る。
夢のように楽しい時間を過ごしていた。
そう、まるで、親友のように。
(まずい)
カカシが、イルカを横目で眺めながら、唇を噛みしめる。
カカシは、気づいていた。
前回のバレンタイン。
実はお互いに、「好き」だと伝えていない事に。
勿論カカシはそういうつもりだった。
一世一代の大告白のつもりで、異国でグランプリを取得したという乳牛の買い付けまでしたのだが、もしかしたら、イルカは、いわゆる友チョコという物のためにカカオの木を用意していたかもしれない。
・・・有り得る。
噛んだ唇がじんじんと痛い。
そう、有り得そうなのだ。
牛にぎゅうさくと名付けてしまう、このど天然のイルカならば。
カカシの目にはぎゅうさくとカカオの木。
そして牧歌を楽しむ眩しいイルカ。
これは違う。
いや、これはこれで楽しいが、恋人になって初めてのイベントがこれでは、何か違う。
・生徒を大事にするイルカ先生。
・ナルトを弟のように溺愛するイルカ先生。
・牛やカカオにさえも愛情を注ぐイルカ先生。
・友達を恋人のように大切にするイルカ先生←new!
嫌な妄想が頭をはびこり、こめかみが痛い。
何がnewだ。カカシはイルカの恋人なのだ。友を超えた…はずなのだ。
と、自信をもって言えないのが、カカシの。そして、イルカのイルカたる所以である。
カカシは、これではいかんと、このホワイトデーにかこつけて奮起するのである。
・・・
「好き好き好き好き好き好きっききききすすいきs」
カカシは口の中で必死に、イルカの前で言おうと練習を繰り返す。
壁に向かってブツブツいっていれば、背後ではイルカがニコニコしながら、ぎゅうさくチーズを冷蔵庫から取り出していた。
何やら料理を作るつもりらしい。
思えば、こんな僻地の別荘でよくこれだけの物を作れたな、と思うほどの料理がイルカから紡ぎ出されていた。
なんでもかんでも、材料から手作りしてしまうのは、どうやらイルカの性分のようだ。
(でも、枕が合わないと言ったら、昼間に打ったソバの殻でそば殻枕を作りだしたのには流石にビックリしたけど)
しかも、絶妙な高さが心地よくて、そのまま里に持って帰ろうと思う程だ。
正に、生活の知恵の生き字引。
「どうしたんですか?カカシ先生。元気ないですね?」
考えすぎていたのか、心配そうに顔を覗き込むイルカに、ハッとなってカカシも苦笑する。
「いや、イルカ先生はなんでも手作り出来て凄いなって思って」
「あー、そうですね。手作りは好きなんですよ」
「誰かの影響ですか?」
「ええ、親の影響ですね」
「へー!お父さんとお母さんも手作り派だったの」
その影響が、今こうしてカカシにも行使されているのだとすれば、なんだか自分もイルカの家族になったようで嬉しい、なんてニヤニヤしてしまう。
が、すぐに「いえ」と手を翳して否定される。
「いたずらを仕掛ける時、大体は家の中の材料が減っていてバレる事が多かったんですよ。うちの親は鋭いわ大人気ないわで、俺のいたずらも忍者の技を駆使して逃げたり壊したりしてきたもんだから俺も意地張っちゃって。材料の減りでバレるなら、外から調達して自分で作るしかなくて。近所の松の木とか手頃な材料になったんでいつも折ってその家のオヤジに怒られ」
「うん、わかったから黙って」
相手はイルカである。うっかりと忘れる所であった。
「そういうカカシ先生だって、手作り好きですよね?でないと、わざわざチョコを手作りなんて」
イルカの問いに、たしかに、とカカシも頷く。
「そうですね…俺も思いを伝えるのには、手作りが一番って刷り込みが…。ああ、俺も父さんの影響かも」
「サクモさんが!」
興味津々に目を輝かせるイルカに少し照れながら、頭の中では遠き日の父を思い出す。
懐かしい父の姿に思いを馳せて、ああ、自分も、あの頃の父の気持ちに寄り添えるようになったんだなと温かい気持ちになってくる。
「父親が母親にプロポーズするとき、ダイヤの鉱山を買い取って、一人で」
「判りました。うん。サクモさんすごいな!」
自分の白い牙の異名をもじって、ダイヤモンドを牙の形に掘って母に渡した所、母に、「まあ頑丈な入れ歯ね!有難う」と言われ、
更に惚れたという話をしたかったのだが、どうやら、させてもらえないようだ。
カカシはこのエピソードを父から聞くたびに、バカップルを通り越したダブルボケ夫婦と呼んでいたのだが、それがカカシの理想の家庭の形となって心に根付いていたとは、無意識とは本当に恐ろしい。
そうこう言っている間に、イルカが何やら作り出す。
どうやらお菓子のようだ。
シャカシャカと楽しそうな音がボールの中で踊る。
「先生、それは何?」
カカシがボールをのぞき込むのに、イルカがニヤリと笑う。
「ティラミスというお菓子を作ります」
「肉食恐竜が間違いを犯しちゃったって感じの」
「ああ、ティラノサウルスがミスを犯す、ティラがミス、ティラミスね。違います」
最近、思考を読まれているのか、イルカに言葉遊びを仕掛けても瞬殺されるカカシである。
これはこれで、仲が良いようなくすぐったい感じが嬉しい。
「ちょうど、ぎゅうさくのミルクで出来た生クリームとチーズがあったので」
「コーヒーもいれるの?」
「生地に染み込ませるんですよ。そうすると苦味が甘さを引き立てます」
「へえ・・・」
「今作っておけば夜には食べられますよ」
「そんな時間がかかるんだ」
「1時間くらいで固まりはするんですけどね。でも、こういうのは冷えてる方が美味しいものです」
「冷えてるほうが…」
「そうそう。待つのもまたお菓子作りの楽しさですよ」
「待つ…」
冷えるのを待つだなんて。
イルカの言葉に、ざわりと胸が騒いだ。
まるで、カカシが恋に飽きるのを待つと言われているかのように聞こえたからだ。
恋人ごっこも、冷えるのを待てば、すぐ終わる、と。
途端に胸に穴があいたような感覚に襲われる。
近づいたと思っていた距離も、本当は平行線だったと思い知る。
早く、言わなければ。
早くイルカに好きだと。
早くイルカと、本当の恋人になりたいと。
でなければ、このまま自然消滅で、イルカはカカシから去って行く。
まるで、冷蔵庫に入れて、冷めるのを待つかのように。
あのティラミスの苦味は、きっとカカシを雁字搦めにしてしまうだろう。
そして、ペロリと食べられ跡形もなく消えてしまう。
その前に。
言わなければ。
「…好きだよセンセ」
口の中から出て行こうとしない声に、「俺もですよー」と遠くの方で能天気な幻聴が聞こえた。
・・・
「好き好き好き好き好き好きっききききすすいきs」
カカシが露天風呂に浸かりながら、水の中でブツブツ呟くのに、イルカが覗き込んでくる。
「カカシ先生、溺れてます?疲れましたか?」
「いいえ、イメージトレーニングです」
「ははあ、流石上忍様。いついかなる時も修行という訳ですね」
「上忍とか関係なく、人間として残りの人生の幸せをかけた戦いに挑むのです」
「なるほど。我々にとっては重要な課題ですね」
「まさしく」
「頑張ってください。俺は先帰りますね」
「へえ」という言葉を残して、イルカが何に納得したのか判らないまま風呂から出ていくのを、カカシは眺めて。
また鼻下まで沈みながらイメージトレーニングを続ける。
実は、好きだと言うのは簡単だ。
しかし、その後の展開が読めない。
なんといっても、あのトリッキーイルカである。
「俺も好きですよ!親友です!」と答えられた時のダメージは計り知れない。
そこからの巻き返しに、どういう言葉や行動をとれば良いのか、が今のカカシのイメトレ内容であった。
1:親友を超えたいと言ってみる。→大親友です!と答えられる可能性が高い。
2:愛してると言ってみる。→友愛とは美しいですね、と答えられるに違いない。
3:襲い掛かる。→火影行き決定。
「うーむ手ごわい」と唸りながらも、口では好きという練習を怠らない。
お湯の中で、カカシの言葉はかき消されながらも水泡を作って浮かび上がる。
パチンと消える泡に、カカシは苦笑した。
しかし。
すぐに、思考をぶち破るような高い鳥の声が聞こえた。
見上げると、馴染みの鳥が上を飛ぶ。
キューイと何回か鳴いた鳥は、カカシの頭の上を一回旋回すると、ひらりと紙を落として飛び去っていった。
湯を避けるように離れた所でひらひら舞ってくる紙を、手を伸ばして受け取る。
カカシは、その内容を確認するや否や、
すぐさま服を羽織って、露天風呂から飛び出した。
嫌な予感はずっとしていた。
事の発端は先日の、紅が行った任務だ。
隊一個分の人数を引き連れて、紅は言葉の通じない異国へと向かった。
そして翌日。
帰ってきたのは、紅をいれてわずか5人だったのだ。
罠だという事は最初からこっちだって判っていた。
ある特殊な知識のあるものを一掃するかのように集めて任地へ行かせるなど、普通では考えられない。
あの時は、多言語を理解できるものが集められた。
その直後。
植物学に長けている者が、動物を使役できる者が、体術が得意な者が、と次々と隊を組んで任地へ飛ばされていく。
人間には得手不得手がある。
ある特定の分野に熟達していれば、必ず、対になる短所があるのだ。
そして、隊をなすほどに集まった彼らは、同じ方向性の知識しか持ちえない。
つまり、不測の事態に陥った時。
さらに彼らの得意分野が使えない場面に出くわした時。
隊はあっという間に崩れてしまうという事だ。
実に回りくどく、そして奇妙な罠だった。
最初にその依頼が来た時から、警戒はしていた。
隊にはバランスが大事だ。
そのバランスを、あえて崩すような内容の依頼。
カカシは【依頼人を調査する】という依頼を請け負っていた。
似た内容の依頼にも関わらず、依頼人は毎回違う。
その依頼人全員に、カカシの影分身が張り付いていた。
今の鳥は、カカシ本体からの命令だ。
今から、行くと。
ここに、カカシが来ると。
イルカの元へカカシが来ると。
そう。
『依頼人の一人であるイルカ』の元へ。
カカシは、急いで別荘内にいるイルカの元へ瞬身の術を切る。
・・・
「イルカ先生…」
イルカは台所にいた。
手にはワイングラスに綺麗に盛り付けられたお菓子がある。
「あ、カカシ先生、さっき作ったティラミス、うまく出来ましたよ!!見てください、この完璧な層のハーモニー!」
両手に掲げるように見せてニコニコ笑うイルカに、心が痛む。
「先生…」
「ほら、甘いの食べると元気になりますよ!風呂上りですよね、冷えててちょうどいいはずです」
そんなイルカの言葉もろくに聞かず、
差し出すイルカの手をすり抜けて、カカシがイルカを抱き寄せる。
イルカは突然のカカシの行動に驚いて、両手にティラミスを持ったまま固まってしまった。
「か、カカシ先生!?」
「イルカ先生…」
慌てるイルカの体を両手で強く拘束して。
そして、すぅっと。
イルカの背に回した手で、首筋にクナイを突き付けた。
「カカシ先生」
二回目に呼びかけてくるイルカの声は酷く冷静だった。
「ねえ、誰が依頼主なの?」
イルカの体がわずかに身じろぐ。
「あの任務、イルカ先生が発案者?ねえ、どこからどこまでが貴方の策なの?俺の事も、嵌めようとしていたの?」
カカシの心がどんどん暗くなる。
自分の言葉に傷ついて。自分の考えが追い打ちをかける。
一番、裏切ってほしくない人が敵だったなんて、誰だって考えたくない。
「先生…好きだよ」
言いながら、カカシはイルカのうなじに刃をあてた。
「帰ってこなかった残りの仲間は、どこにいる」
イルカはくすりと笑う。
「ああ、このカカシ先生は、本物なんですね。じゃあ言う相手を間違えてたんだ俺」
イルカの声はいつも通りの明るさで。
そして息を上げながら、イルカの目の前に立つカカシの影分身にイルカは微笑んだ。
「ね、カカシ先生。さっき作ったティラミスうまく出来ましたよ。風呂上りにどうですか?」
途端に、腹の底から苛立ちの塊がせりあがって来て、カカシは勢いに任せて自分の影分身にクナイを投げつける。
クナイは影分身をかき消しながら、床へ刺さった。
「先生」
「何が聞きたいですか?」
静かな声が耳そばで囁かれる。
「全部」
それに間髪入れずに答える。
全部だ。勿論全部に決まってる。
「目的、依頼主、仲間の行方、あなたの真意。全部に決まってる」
「そうですね…」
イルカはため息のように息を吐くと、するりとカカシの腕の中から身をかがめて出ていく。
「先生」
「じゃ、そこにどうぞ。話しましょう」
台所の椅子にカカシを勧めるイルカは。
まるで受付で依頼を言い渡すかのようだった。
****
台所の机に、二人で向かい合わせに座る。
「まず、俺の依頼主は、火影様です」
「…」
「カカシ先生の依頼主は?」
「…ホムラ様です」
互いが頷く。
「…そうか…まさか、カカシ先生がホムラ派だったとは…」
「それはこちらのセリフです。まさか先生が火影派だったなんてね」
「カカシ先生は、写輪眼関連ですか?」
「まあ、そうですね。イルカ先生の方が意外だよ。てっきり働きすぎとかで何かしら健康診断引っ掛かると思ってたのに」
「残念ながら、全てがA判定でした」
「むううう、悔しい。けど、それはそれで嬉しい」
時間は、バレンタインの前の週に戻る。
火影である三代目と、ご意見番のホムラは里の現状を憂いていた。
ちょうど居合わせたカカシは、二人の愚痴を聞かされ、なかなか帰れない状況に些かぐったりとしていた。
「まったく、バレンタイン?浮かれおってからに、最近の若者はけしからん」
ホムラのセリフに、三代目も深く頷く。
「全くじゃ。・・・と、そういえばカカシも。お主、異国まで牛を買いに行ったそうじゃないか」
「はあ…」
「なんじゃとう!?まさか、バレンタインに関連するんじゃなかろうな」
「いや、しますね」
「っかーーー!なんということじゃ。緊張感が足りん!里にいようともお主らは忍じゃろうが!」
「はあ…しかし、たまにはお祭り騒ぎをするのもいいじゃないですか」
こんなイベントがなければ、告白することもままならない位に忙しいのだ。
1年に一度くらい、本気で遊んだっていい、とはカカシの意見である。
「イルカの奴も何やら企んでいるようだしのう。あやつは昔からいたずら癖が抜けんで困る」
「嘆かわしい。たるんどるのお…よし、ここはひとつ、里の忍たちに儂らが気合いをいれてやろうじゃないか」
ホムラの思いつきに、三代目が食いつく。
「ほほお?どうするんじゃ?」
「里の忍ども同士で競わせよう」
「おお、面白そうじゃな」
「忍をまず、二チームに分ける。で、相手のチームの忍を多く倒した方が勝ち」
「いいのういいのう!じゃあ、どうチームを分けようかの!」
「おあつらえ向きに、健康診断が明日あろう。それの結果で分かれるというのはどうじゃろう」
「面白い!早速通達じゃ!」
つまりは、バレンタインという恋のイベントに全く興味も関係もない老人たちが拗ねた結果、こうしたよく判らないイベントが同時開催されることになったのだ。
イルカは、健康診断でA判定組火影チーム。
カカシは、健康診断で要再検査組ホムラチーム。
期限はホワイトデーまで。
チーム分けされた忍たちは、お互いがどちらのチームかすら判っていない。
そんな状態で相手の戦力を削いでいく。そして最終日にメンバーが多く残っていたチームが勝利。
そんなゲームだった。
勿論、本当に決闘などをすれば、強い上忍がいるチームが勝ってしまう。
そのため、《ケイドロ》のルールが採用された。
つまり、罠に引っ掛かった忍たちは、敵チームのとある場所に隔離されるのだ。
隔離された忍たちは、誰かが助けるか、ゲームが終わらない限り、そこから動くことはできない。
つまり、せっかくのバレンタインデーやホワイトデーを、隔離されて過ごす忍が多数現れるということだ。
それが、浮かれた若者たちへ喝をいれたい老人たちの思惑だったのだから、老獪としか言いようがない。
「紅や一緒に帰ってきたあの5人の仲間は、火影チームだったんだね」
「その通りです」
「ねえ、仲間の居場所はどこ?どこに隔離しているの?」
「あと少しでゲームセットです。それが終わったらお教えしますよ」
「今の所、うちのチームは負けてる?」
「さあ?俺には判りかねます」
「うそだ。忍を管理している受付忍がどっちのチームでも参謀になっているって聞いたよ。火影チームはイルカ先生でしょ」
「ふふふ、そうですねえ?」
「ねえ、先生。いい子だから」
カカシが出来るだけ優しく、イルカの頬を撫ぜる。
それにイルカは少しだけ気持ちよさそうに目を細めるも、しかしニコリと笑うだけだった。
いつもは心の声まで駄々漏れのイルカが、こうして口を閉ざしているということは、彼は今、忍モードだ。
この別荘にきた瞬間から、それは始まっていたに違いない。
最初からイルカには、カカシは敵だと知っていたという事なのだ。本当に侮れない。
「ほら、カカシ先生。とりあえずティラミスをどうですか?」
「先生、俺たちバレンタインデーで付き合う事になったよ?他の忍たちにも幸せを分けてあげようとは思わない?」
「おやおやー?さっきまでのカカシ先生は、俺と本当に付き合ってるのか疑ってましたけど?」
「だってあの影分身は、バレンタインデー直後に作った奴だもの。その後の俺たちを知らないから仕方ないよ」
「あんな純情なカカシ先生もいたんだなって少し感動していました」
「バレンタイン前の俺はあんな感じだったんだよ可愛いでしょ?さ、他の恋する忍たちにもチャンスをあげようよ」
「そんな事いって。この勝負に勝ったチームに与えられる商品を知ってるからそう言ってるんでしょ?」
にやりと笑うイルカに、カカシも苦笑する。
「そりゃあ、ねえ…?」
「俺だって興味ありますもん。勝ちに行きますよ」
「うーん…じゃあ仕方ないなあ…」
「仕方ないですねえ…」
ピキンと二人の間に緊張が走る。
そして、間をおかずにカカシが、ガンと机を叩いた。
「ティラミス早食いで決闘はどうだ!」
「のった!」
そうして、13日の夜が更けていったのである。
・・・
かくして、14日の当日は里中が大変だった。
普段、バレンタインやホワイトデーを意識していない者まで頑張る事態となったためだ。
当日、里に残っていた、いわゆる逃げ切った勝ち組の忍たちは、こぞって告白劇を繰り広げ、
成功すればよいが、勿論玉砕した者も大勢現れた。
また、囚われた忍たちも、囚われた者同士で致し方なくくっついたりと、悲劇と喜劇のダブルパンチで、阿鼻叫喚の様相があらゆる所で繰り広げられたのだ。
更に。
この一か月、お互いを疑い警戒しながらの生活をしていたために、付き合っていたカップルの破局率も大幅に上がってしまうというオマケまでついてきた。
当然、任務達成率もさがった。
そのため、諸悪の根源である、三代目とホムラはイルカ達受付忍に説教される羽目となったのである。
そこで、勝者であるイルカチームの要請で、火影はこう宣言した。
「バレンタインデーとホワイトデーのやり直しを一週間後に設ける」と。
勝者チームへの商品は、火影に一つ、願いをかなえてもらう権利だった。
参加していた忍のほぼ全員が、中長期の休みを切望していた。
が、今回の火影たちの陰謀により、里の恋愛事情はめちゃくちゃになってしまった。
だから、この一か月をなかったことにして再度仕切り直そう、というのがイルカ達の要求となったのである。
「ほら、いつまで拗ねてるんですか、カカシ先生」
部屋であぐらをかいて、いつもの本を読むカカシに、イルカが声をかける。
驚いた。
拗ねてる様子なんて、見せていないと思っていたのに。
「拗ねてなんか」
一応、そう伝えてみるが、イルカにはバレバレのようだ。
「いいえ、拗ねてますよ。そんな悔しかったですか?早食いに負けたの」
「だって、あんなに甘いと思わなかったからね…」
嘘だ。
食べた事のない未知の食べ物ティラミス。
コーヒーの苦味は、カカシの苦手な甘みを消してくれていると思った。
あるいは、甘かったとしても、修行の一環だと思えば耐える事が出来るものだと思った。
ところが、一口食べた瞬間に、その思いが打ち砕かれた。
お菓子が甘かったんじゃない。カカシの考えが甘かった。
カカシのために作られたティラミスは、
カカシ好みに甘すぎず、とろけて。
程よい苦みがアクセントになって。
そして、なにより冷たくて美味しかった。
早食いなどしたら、勿体ないと思うほどに。
そもそも、イルカの作った食べ物で早食いなど、カカシには最初から勝機などなかったのである。
「全く。こんなのいくらでも作ってあげるのに何を考えてるんだか。はい、カカシ先生。ティラミスどうですか?」
いつものように心の声まで駄々漏れにさせながらもイルカの手には、あの時のようにティラミスが乗っている。
別荘の時のようにおしゃれなグラスには入っていなかったが、しかし、間違いなくイルカの作ったイルカのお菓子。
肩をすくめてイルカから受け取った器は、やはり程よく冷たかった。
少しばかりささくれて熱をもった心に、ちょうどいい。
別に早食いに負けた事などどうでもよかった。
ただ、あの時、自分の影分身が考えていた事がどうしても心をひっかいていく。
ティラミスを作るイルカを見て、イルカの気持ちが冷めると勘違いした自分の影の気持ちはよく判る。
あの時、焦った気持ちは、確かにカカシの気持ちだった。
イルカは誰にでも優しい。
それはイベントのやり直しを要求した所からも見て取れる。
もう一度、恋する忍にチャンスをと。せっかくの特権を使って仲間のために気を配る。
それは、いささか行き過ぎた愛だと、カカシは思う。
友達どころか、会話をしたことさえもない仲間のためにイルカは優しさを振りまくのだ。
まるで恋人を甘やかすように。
でも、それでも。
目線を落とすと、そこにはイルカのティラミス。
手の中のそれは、カカシの体温を少し奪いながら、するすると体に入ってくる。
こうして、カカシの体調や気持ちを一番に考えて、タイミングよくティラミスを出してくれるのはカカシだけの特権なのだ。
「ね、先生、好きだよ?」
呟くようにカカシが言うのに、イルカもニコリと笑う。
「俺も好きですよ!大親友です!」
「う・・・」
今このタイミングでイルカに言えば、こう返されるとは思っていたが、実際言われると本当にダメージが凄い。
冗談と判ってはいてもこれだけの衝撃なのだから、あの時、同じ事を言われていたら立ち直れなかったに違いない。
イルカが笑いながら、落ち込むカカシの頭を撫ぜる。
「皆もうまく行くといいですね、やり直しバレンタイン」
皆も。
そのたった一言だけで救われる。
自分たちはうまく行っているのだと、隠れた言葉がカカシを安堵させる。
最近、イルカはこうした小さな言葉遊びをしかけてくる。
それは、きっとカカシに影響された癖で。
カカシは、弄ばれてるなあと思いながらも「そうだね」と苦笑する。
そして、残りのティラミスを口にいれるのだ。
ティラミス。
怒りや悲しみで熱くなった体を冷やして。
苦さで叱り、甘さで慰めて。
そうして、私を元気づけて。
一週間後、里では、泣きながらティラミスをバケツ食いする里民が急増したのは、また別の話である。
<終>
拍手ボタンを4/3に撤去いたしました。
スポンサードリンク